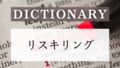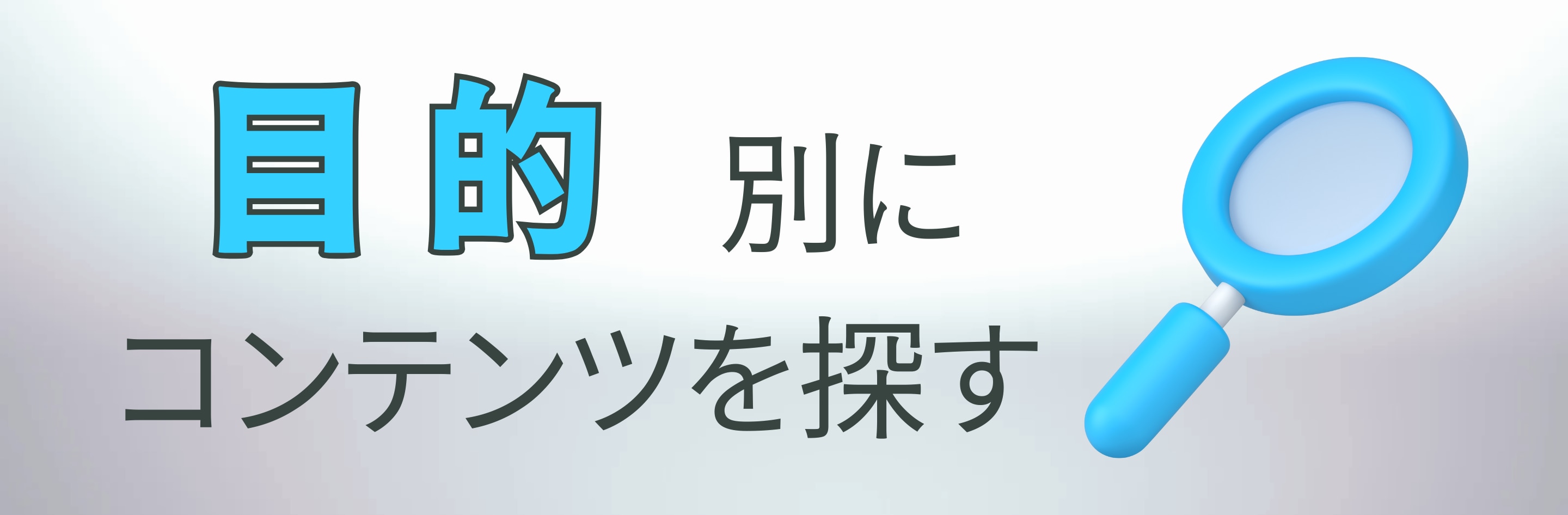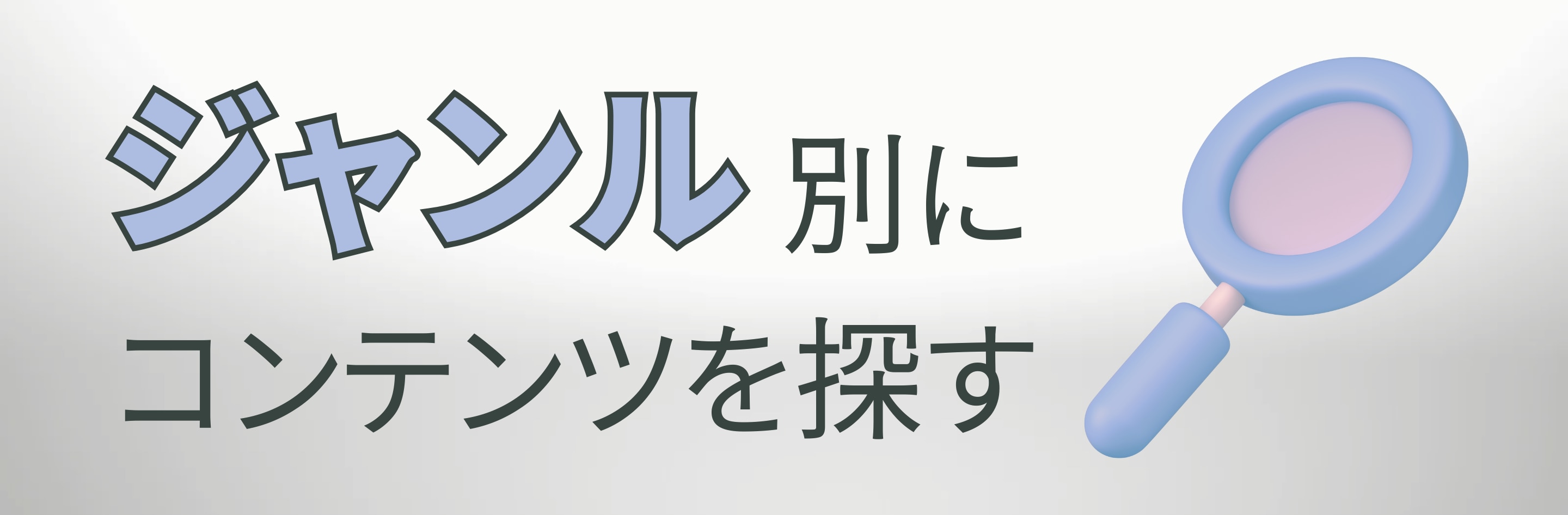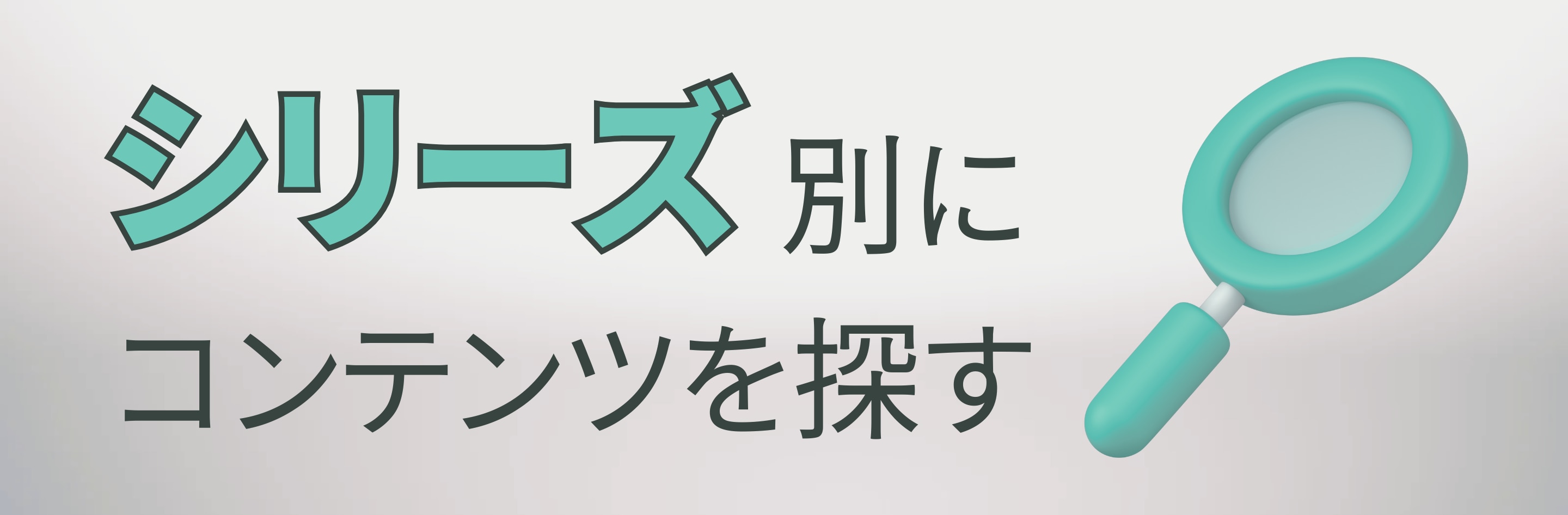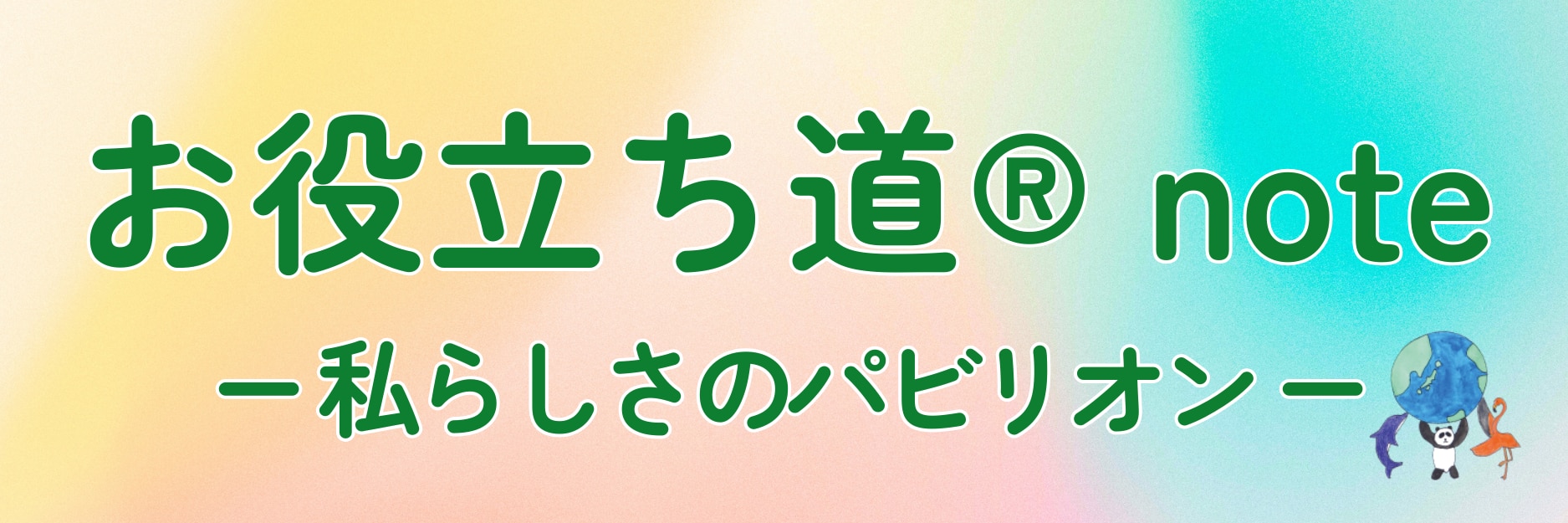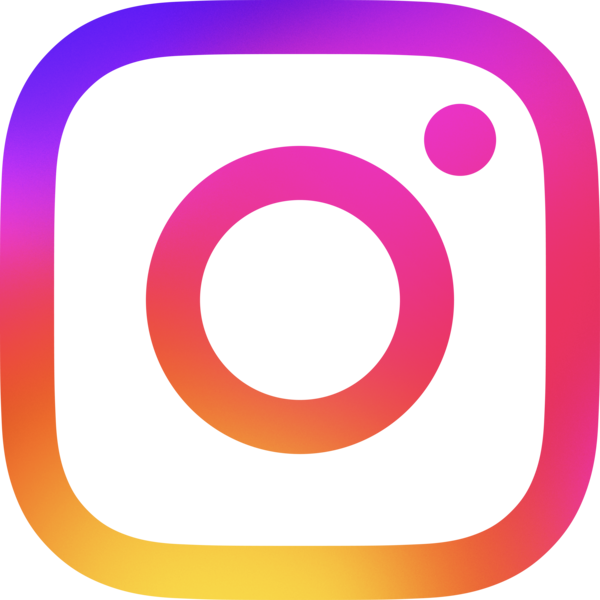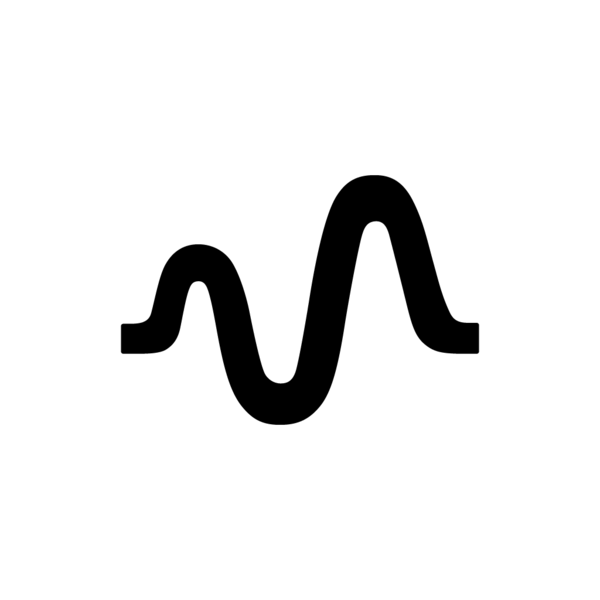入社3年目の仕事への向き合い方
こんにちは、小川ひなたです。入社して3年。毎日が“新しい”の連続だった1年目、がむしゃらに走り抜けた2年目。そして3年目の今、自分のこれからについて考えることが増えました。今回は「入社3年目の分岐点」をテーマに、仕事との向き合い方について考えてみたいと思います。
目次[非表示]
分岐点は“できる・できない”より“どう向き合っているか”
結論から言えば、3年目以降に評価されるかどうかは、「スキルの量」よりも「スタンス(どう向き合っているか)」に大きく左右されると感じています。
なぜ「3年目」が分岐点なのか?
社会人3年目は、仕事の基本スキルや社内の人間関係に慣れてきた頃です。
新人扱いされることも減り、任される仕事の難易度も上がってくる
後輩ができ、自分の言動が周囲に影響を与えるようになる
「今の会社で成長できるのか」「キャリアの方向性は合っているのか」と迷い始める
こうした背景から、仕事の捉え方そのものを見直すタイミングでもあるのです。
キャリアの分岐点で感じる、焦りと違和感
最近の事例ですが、同期のAさんが大きなプロジェクトを任されたという話を聞きました。
正直、焦りました。私はまだ、任されるというより“サポート側”。
「私、何が足りないんだろう」
「もう3年目なのに、まだここ?」
ぐるぐると何が正しいのかがわからないまま、転職という選択肢も頭をよぎりました。
でも、すぐに“場所を変える”ことが、私にとっての正解なのか、わからなかった。
評価の分かれ目は、“スキル”よりも“スタンス”
そのような中で、上司からふとこんな言葉をもらったんです。
「小川さんって、すごく“どう向き合うか”を大事にしてるよね」
「そういう姿勢は、必ず誰かが見てるし、仕事の質を底上げするんだよ」
え? 私、そんなふうに見られてたんだ。
できる・できないにばかり目を向けていたけど、
“どう取り組むか”の方が、ずっと大切なんだと気づかされた瞬間でした。
「できる人」より「向き合っている人」が信頼される理由
ここで大切なのは、「できる・できない」よりも、「どう向き合っているか」。
これは、多くの先輩社員やマネジャーが口をそろえて語る“評価の本質”です。
例えばこんな違いがあります。
周囲からの 見られ方 | 行動例 |
仕事ができる人 | 言われたことを正確にこなす、ミスが少ない |
仕事に向き合っている人 | 仕事の背景を理解しようとする、ちょっとしたことから学びを得ようとする、仲間や後輩を気にかける |
「仕事ができる人」ももちろん大切ですが、「向き合っている人」には、一緒に仕事をしていきたい、一緒に学んで仕事ができる期待感が持てるという印象がありますね。
自分自身の変化の兆しを知るには
「ちゃんと向き合っているのかな」と不安になる時ほど、
一度立ち止まって周囲からどう見られているかを考えてみましょう。
後輩から相談される機会が増えていないか?
上司から「最近、変わったね」と言われたことはないか?
評価されるより先に、“信頼されているかどうか”に意識を向ける
周囲からの小さなフィードバックは、
「向き合い方の質」が変わってきたサインかもしれません。
問うべきは「何ができるか」ではなく「どうありたいか」
入社3年目の分岐点は、
「何ができるか」ではなく、「どう向き合うか」が大切な時期だと思います。
そしてその“向き合い方”は、
環境や他人ではなく、“自分で決められる”もの。
自分で決められるって素敵なことですね。