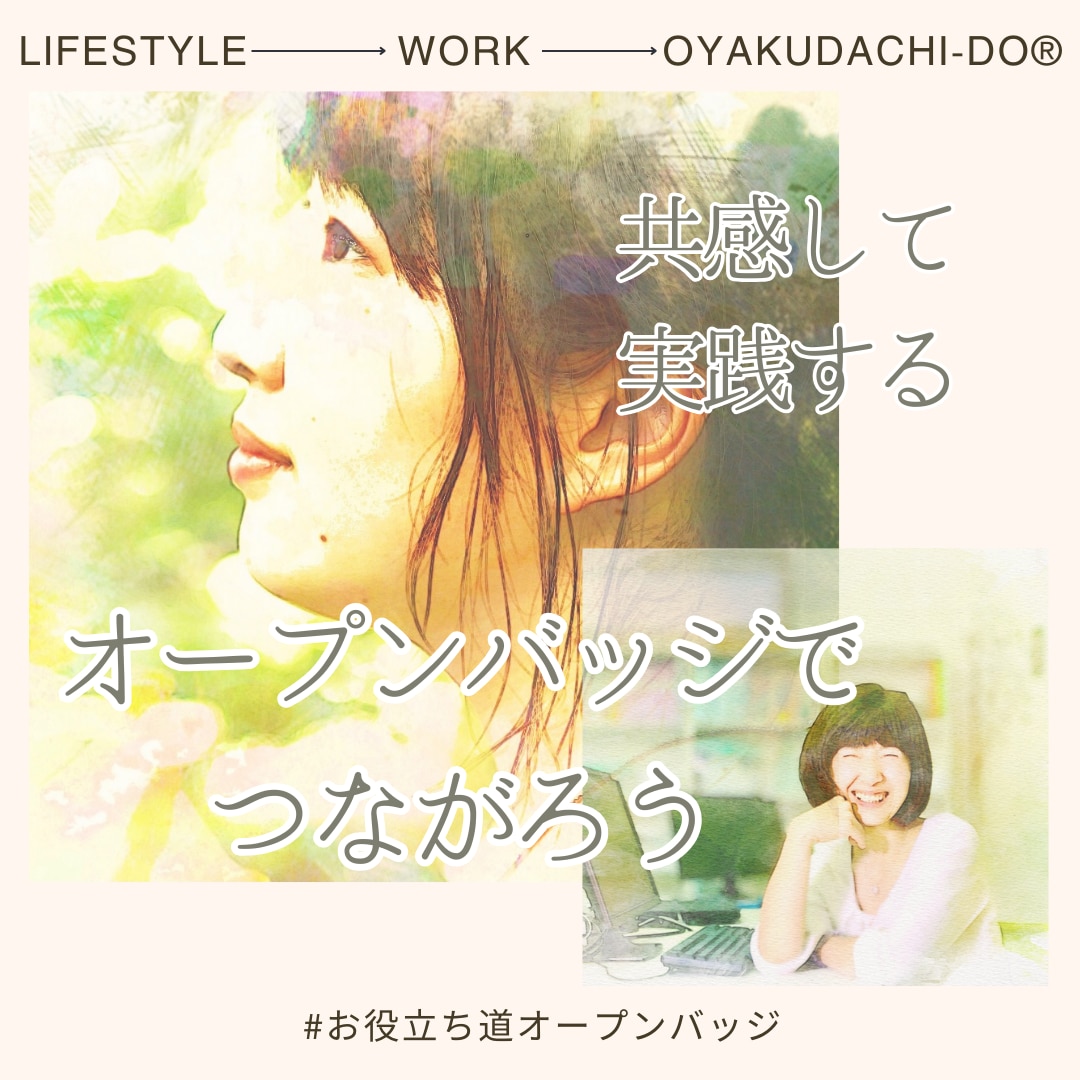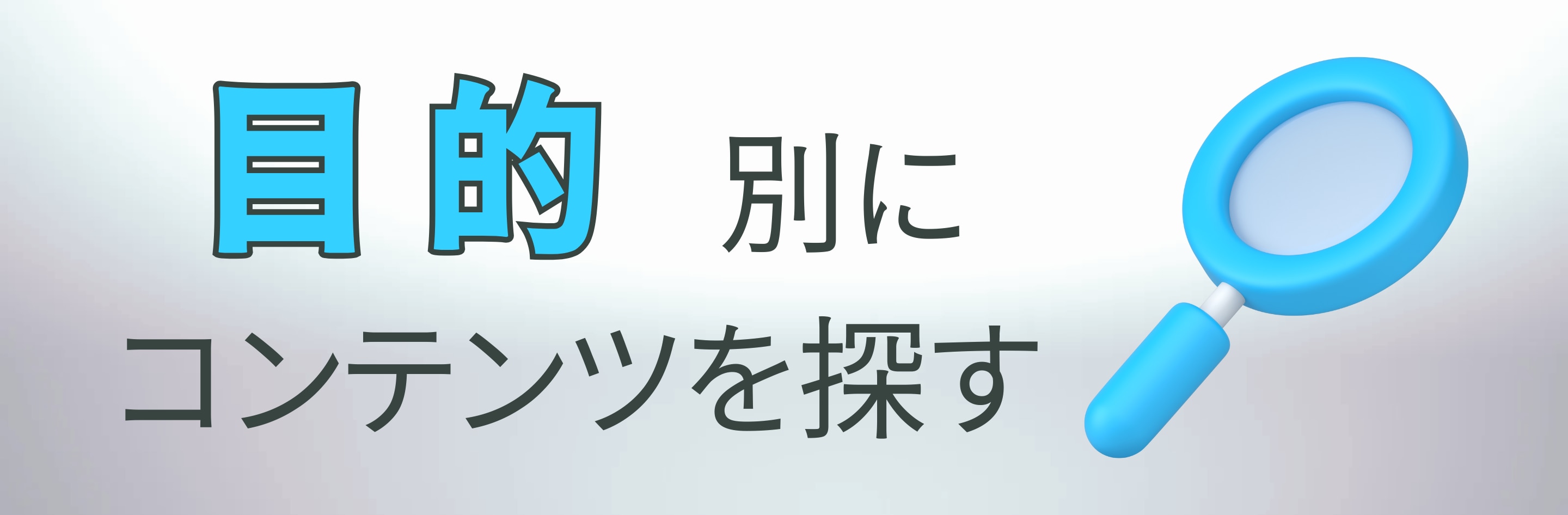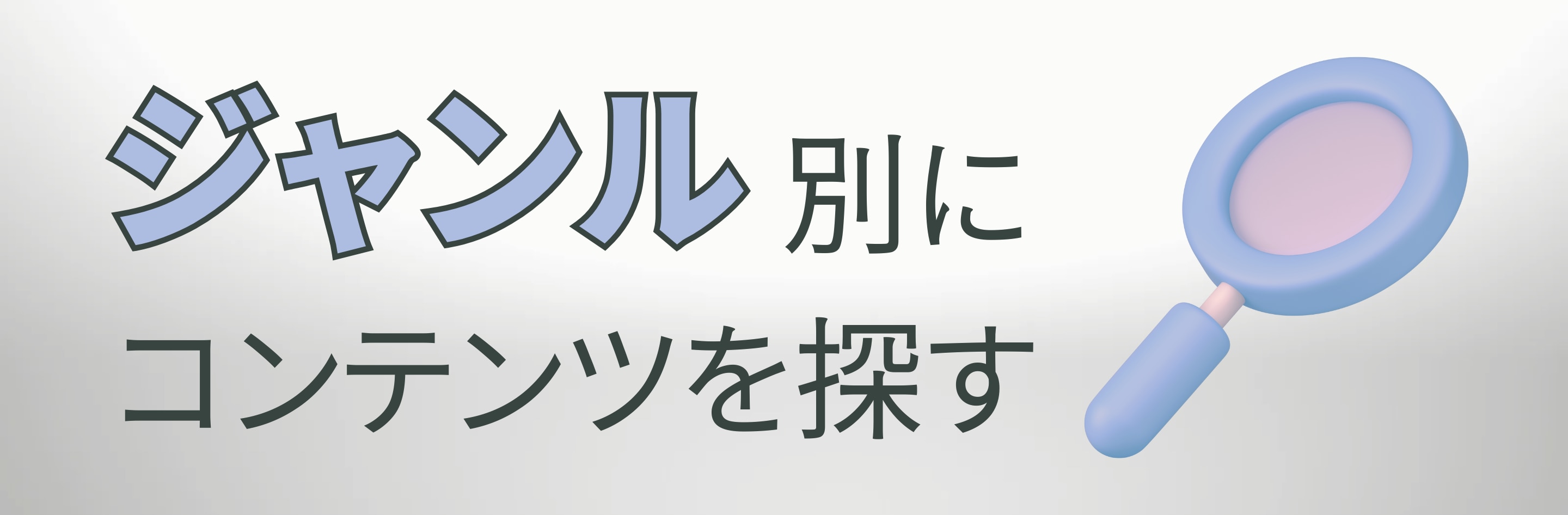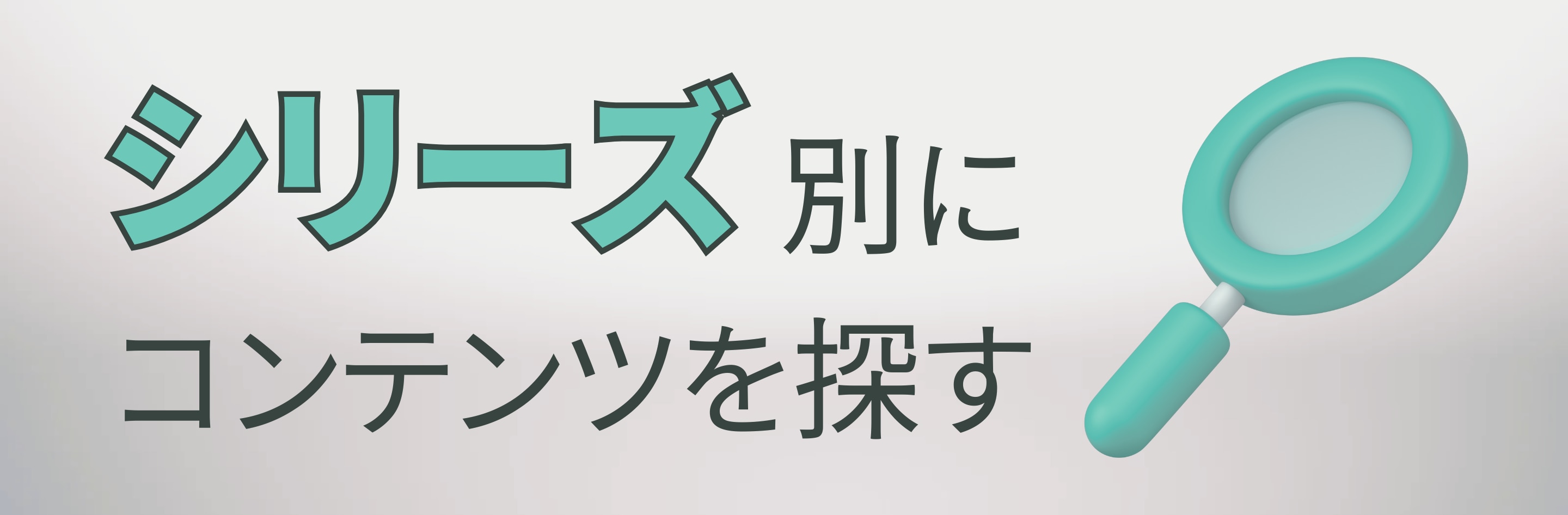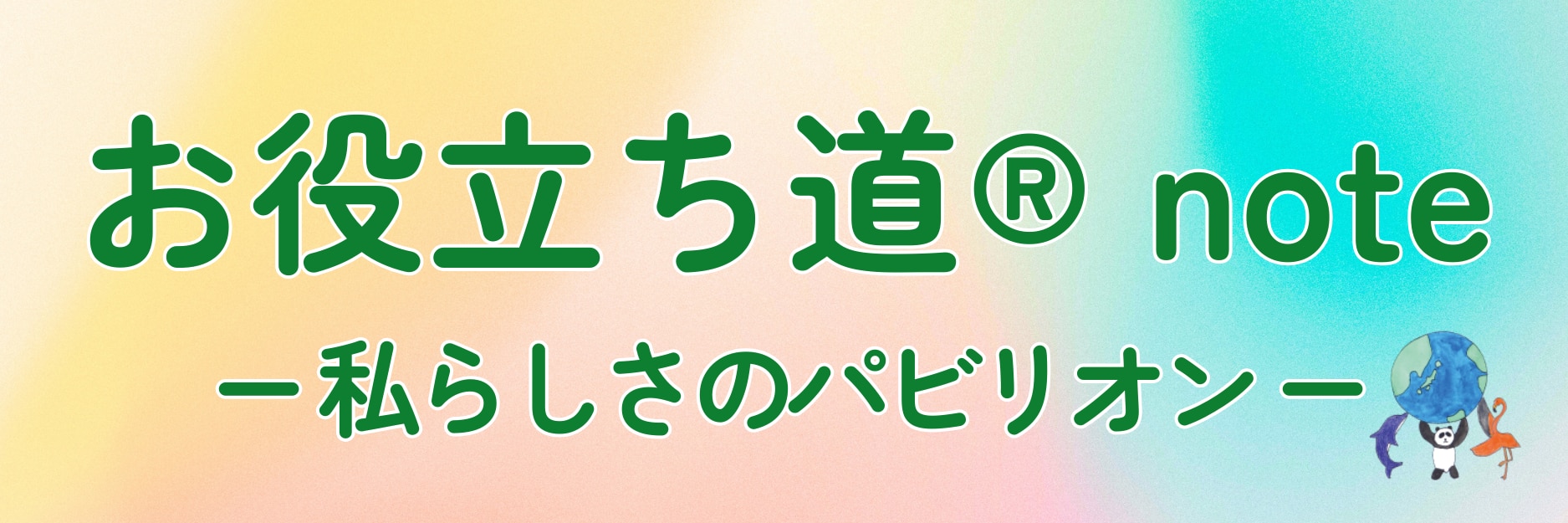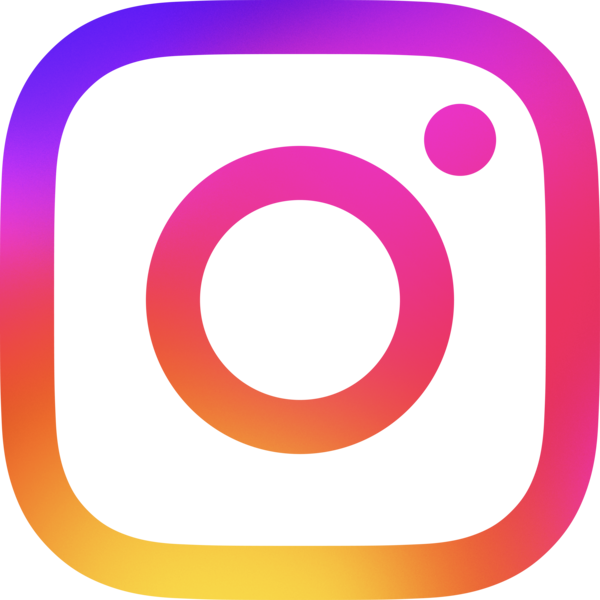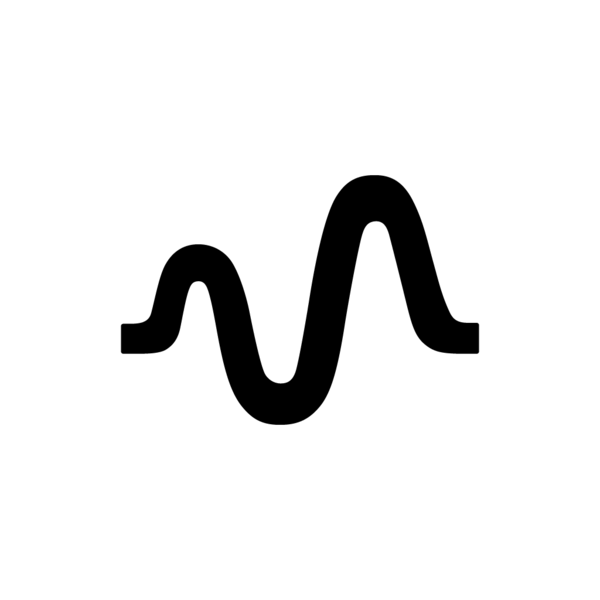キャリアと人生、その間にいる、20代へ
社会人になってからの3年──
慣れた仕事、人間関係、“できること”が増えてきたという実感がある。一方で、ふとした瞬間に「このままでいいのか?」という問いが胸をよぎる。
それは、規模の大きな転換を意味しているわけではない。
ただ、小さな違和感。「昨日の自分」と「今日の自分」が、少しだけズレているという感覚。
このズレこそが、「その先」への視点をひらく鍵になる。
目次[非表示]
「成長」ではなく「変化」に注目する
多くの20代は、「もっとスキルを上げなきゃ」「もっと成果を出さなきゃ」という“成長”のプレッシャーに晒される。だが、成長=右肩上がりのグラフである必要はない。
むしろ、自分の中に「少し変わったな」と思える出来事があるなら、それこそが意味のある「変化」だ。
たとえば、仕事を頼まれたときに前より手際よく動けたとか、苦手だった問いに対して「どうしてだろう?」と自分で考えるクセがついたとか。
こうした“質的変化”に目を向けることで、キャリア=昇進・昇給だけという見方を超えて、働き方や人との関係性、ライフスタイルそのものに価値を見出せるようになる。
「未来」を“予測”ではなく“設計”として捉える
10年後どうなっているかを当てることは誰にもできない。
だが、“どうありたいか”は自分で設計できる。
自分が心地よく働いていられる場所、私生活で大切にしたい時間、人との関わり方。それらを言葉にしてみる。
そうすると、「こうなっていたい」という理想像が見えてくる。
もしもその通りにならなかったとしても、それを“失敗”と捉えず、「こうならなかったらどう動こうか」という選択肢があれば、未来は不確実なものではなく、自分の手で動かせるものになる。
「視点」を増やすと「選択肢」も増える
同じ会社・同じ業界・同じメンバーの中だけで考えていると、どうしても視野が限られてしまう。
だからこそ、意識的に異なる視点を取り入れる。異業種の先輩と話してみる、普段読まないタイプの本を手にしてみる、SNSで「こういう働き方もあるんだ」と感じる姿を探してみる。
視点が変われば、今の環境の見え方も変わる。そして、選べる道も増えていく。「答えがひとつじゃない」ということが、むしろ自由の証になる。
“いまできること”を、小さく試してみる
未来を描き、視点を広げたら、次は“動く”段階だ。
ただし、準備完璧でなくていい。副業を少し調べてみる、社内で異動希望を出してみる、学び直しの講座を見てみる──小さな「試し」の一歩を踏み出す。もし合わなければ、そこで止めてもいいし、戻ってもいい。
大切なのは「可能性を閉じないこと」。小さな動きの累積が、思ってもいなかった扉を開くこともある。
「肩書き」より「役割」
結び(クロージング)
「このままでいいのか?」という問いに、答えはひとつではない。むしろ、答えが出ないまま動き続けられることこそが、20代の強みでもある。
今の自分を否定せず、少しずつ“その先”に目を向けていこう。
変化を捉え、未来を描き、視点を増やし、試してみて、自分が担いたい役割に気づく──そのプロセスが、あなた自身の“集大成”になる。
立ち止まらず、でも焦らず。進み続けるあなたでいてほしい。