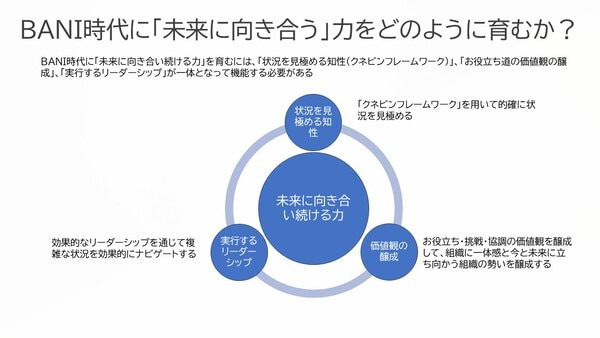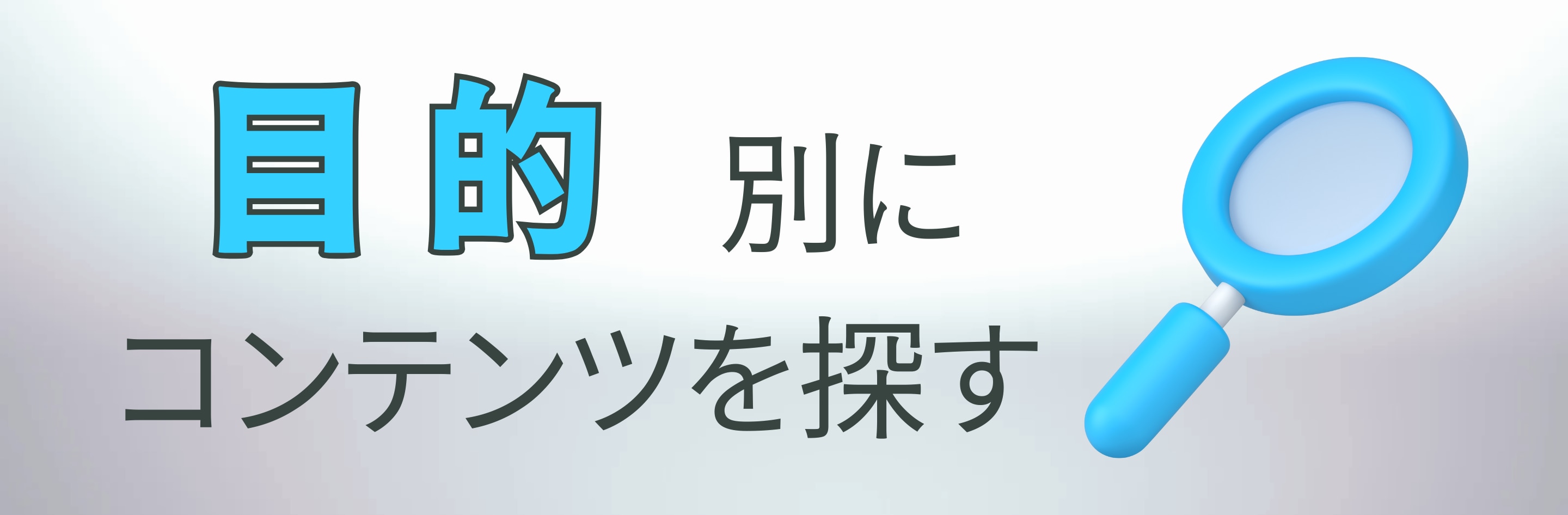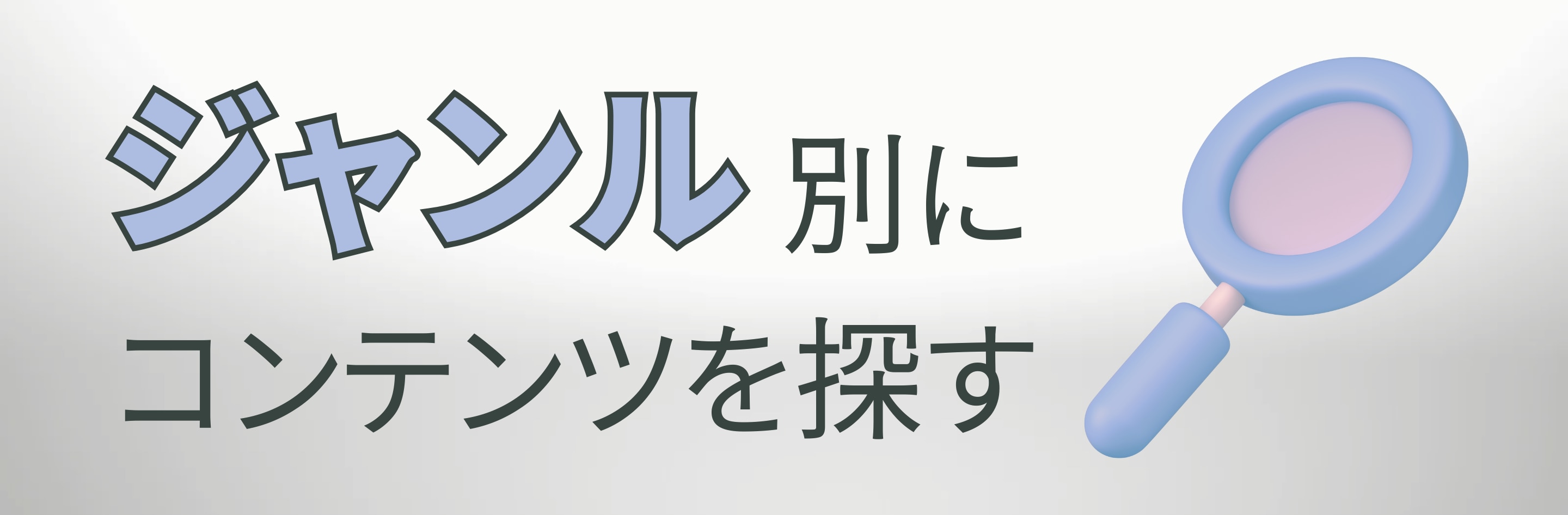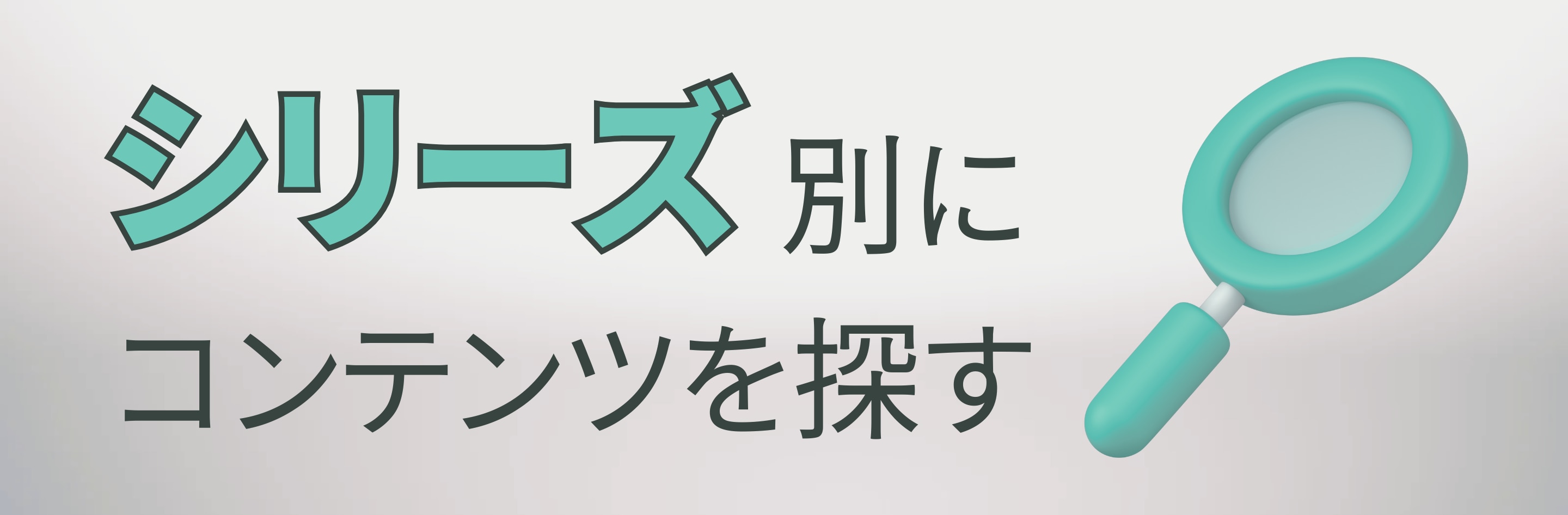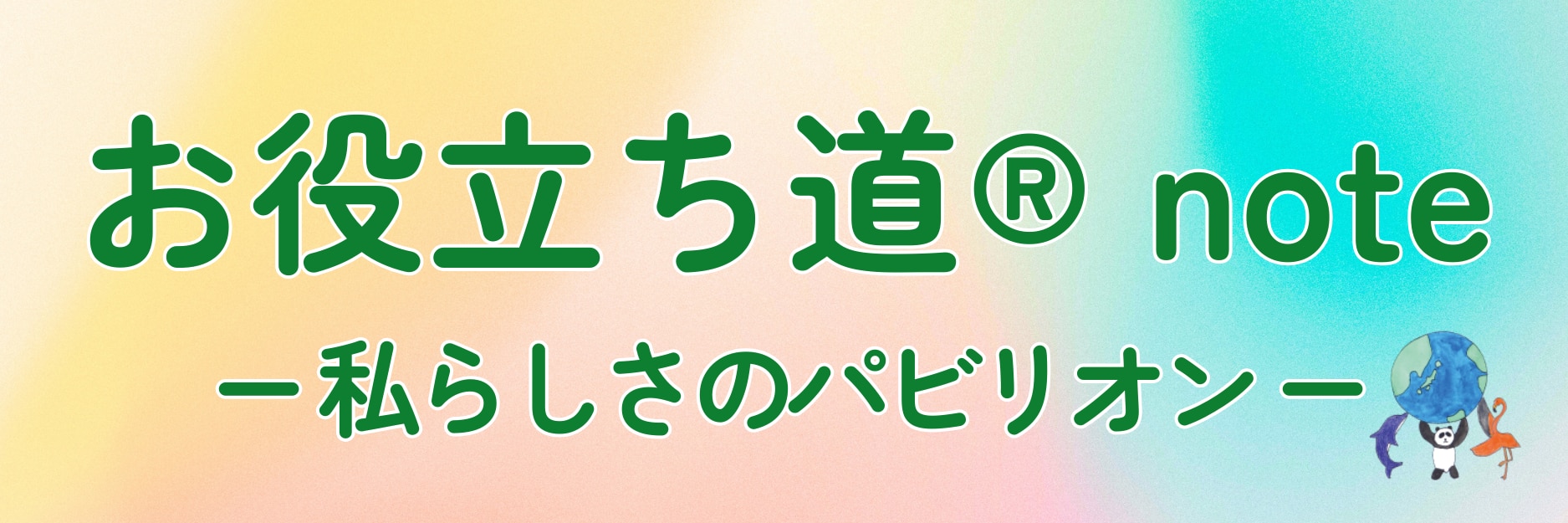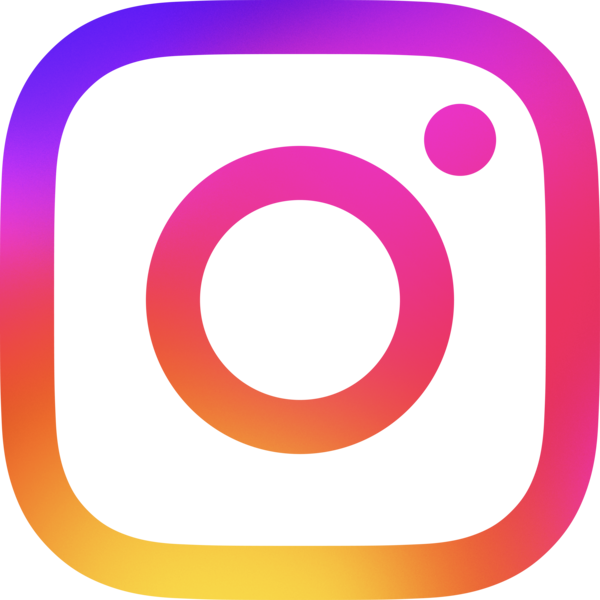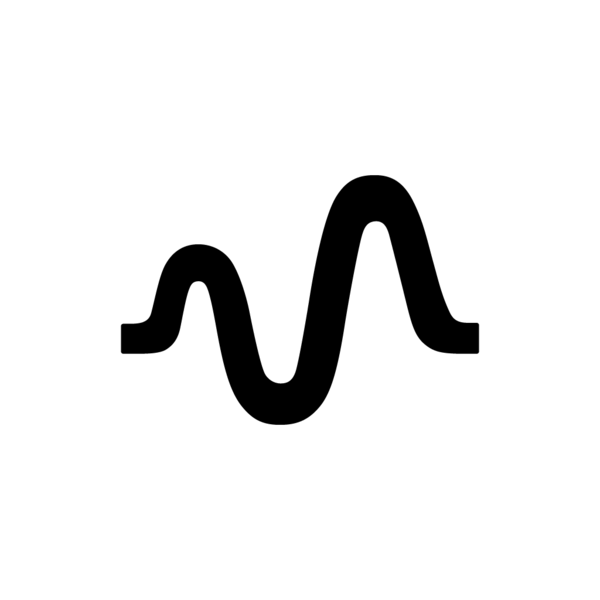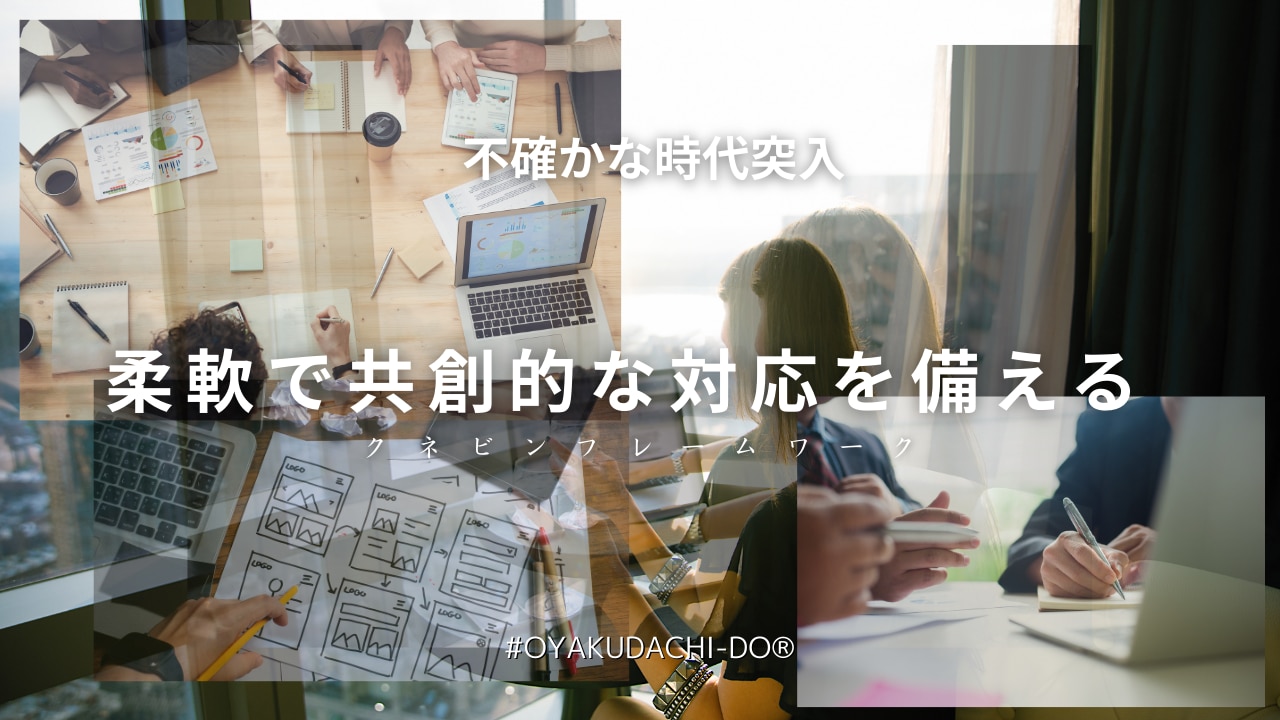
クネビンフレームワークが活きる時代と組織文化
何が起こるのか理解不能な時代、リーダーには「状況に応じてふるまいを変える柔軟性」が求められる。その参考になるのがリーダーシップの姿勢を示す「クネビンフレームワーク」。しかし、どれほど良いフレームやモデルがあっても、良い 組織文化がなければ効果は発揮されない。
目次[非表示]
- 1.BANI時代とリーダーシップ
- 2.より柔軟で共創的な対応力を可能にするには
- 2.1.クネビンフレームワーク
- 2.2.その土壌となる組織文化
- 2.2.1.お役立ち:市場や社会のお役に立とうとする価値観
- 2.2.2.挑戦:あらゆる可能性にチャレンジし続けようとする価値観
- 2.2.3.協調:共創し、協働しようとする価値観
- 2.3.組織文化における3つの価値観の効果
- 2.4.「お役立ち」の価値観による具体的な行動変化
- 3.まとめ
BANI時代とリーダーシップ
BANIとは、現代の環境を特徴づける4つのキーワードです。このような時代における有効なリーダーシップとは、従来型の「計画と管理」のリーダーシップでは限界があり、より柔軟で共創的な対応力が求められます。
図:BANI時代の特徴とリーダーシップの課題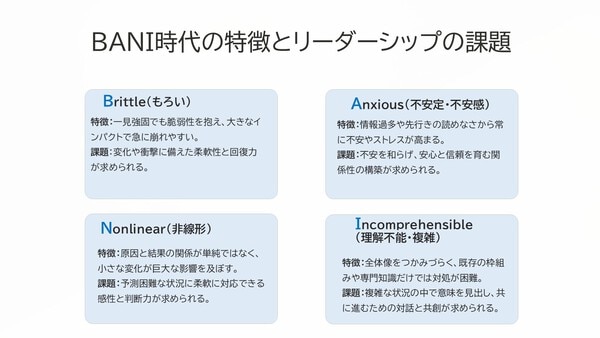
Brittle(もろい) |
Anxious(不安定・不安感) |
Nonlinear(非線形) |
Incomprehensible |
特徴:一見強固でも脆弱性を抱え、大きなインパクトで急に崩れやすい。 |
特徴:情報過多や先行きの読めなさから常に不安やストレスが高まる。 |
特徴:原因と結果の関係が単純ではなく、小さな変化が巨大な影響を及ぼす。 |
特徴:全体像をつかみづらく、既存の枠組みや専門知識だけでは対処が困難。 |
課題:変化や衝撃に備えた柔軟性と回復力が求められる。 |
課題:不安を和らげ、安心と信頼を育む関係性の構築が求められる。 |
課題:予測困難な状況に柔軟に対応できる感性と判断力が求められる。 |
課題:複雑な状況の中で意味を見出し、共に進むための対話と共創が求められる。 |
BANIについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
より柔軟で共創的な対応力を可能にするには
「状況に応じてふるまいを変える柔軟性」を実行できるリーダーシップのフレームワークである「クネビンフレームワーク」とそれを実行できやすい土壌である組織文化をご紹介します。
クネビンフレームワーク
クネビン(Cynefin)フレームワークは、デイビッド・スノーデン(Dave Snowden)によって開発された、問題解決や意思決定のための体系的なアプローチです。
Cynefin とは、ウェールズ語で、生息地という意味です。これは、問題や状況をその「生息地」、つまり文脈や環境の中で理解し、適切な対応方法を選択することを意味しています。
このフレームワークでは、問題や状況を5つの領域(単純、煩雑、複雑、カオス、無秩序)に分類し、それぞれに最適なリーダーシップの姿勢を示すものです。
図:クネビンフレームワークの概要
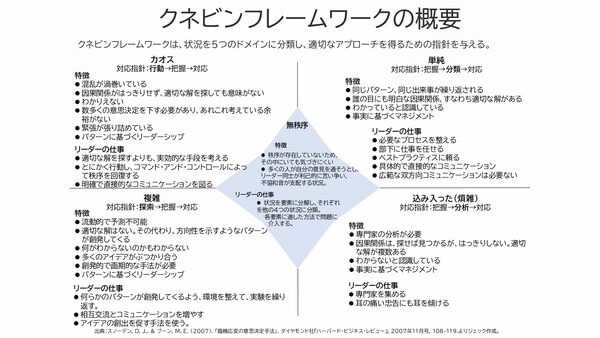
| 単純 |
複雑 |
込み入った(煩雑) |
カオス |
無秩序 |
|
対応指針 |
把握→分類→対応 |
探索→把握→対応 |
把握→分析→対応 |
行動→把握→対応 |
|
特徴 |
・同じパターン、同じ出来事が繰り返される |
・流動的で予測不可能 |
・専門家の分析が必要 |
・混乱が渦巻いている |
・秩序が存在していないため、 |
リーダーの仕事 |
・必要なプロセスを整える |
・何らかのパターンが創発してくるよう、環境を整えて、実験を繰り返す。 |
・専門家を集める |
・適切な解を探すよりも、実効的な手段を考える |
・状況を要素に分解し、それぞれを他の4つの状況に分類。 |
例えば、
- 単純な問題には、定型的な対応が効果的。
- 込み入った(煩雑)問題には、専門知識を活用した分析が必要。
- 複雑な問題には、実験的なアプローチと継続的な学習が重要。
- カオスの状況では、迅速な行動と状況の安定化が優先。
- 無秩序な状況では、状況を要素に分解し、それぞれを他の4つの状況に分類したうえで、各要素に適した方法で問題に介入。
このように、このフレームが教えてくれるのは、リーダーには「状況に応じてふるまいを変える柔軟性」が求められるということです。
しかし実際には、どんなに良いフレームやモデルがあっても、それを実行できる土壌がなければ、効果は発揮されません。
その土壌となる組織文化
組織文化の3つの価値観(「集団性格」:ジェック定義より) を組織全体で共有し育てることが、冒頭で述べたBANI時代において柔軟で意味ある判断と行動を実現する“土壌”となります。
お役立ち:市場や社会のお役に立とうとする価値観
情報過多や先行き不透明さによって高まる不安や孤立感に対して、「誰かの役に立ちたい」「支え合いたい」というつながりと意味づけを生み出す。
挑戦:あらゆる可能性にチャレンジし続けようとする価値観
原因と結果が読めない非線形な変化に対し、小さな試行錯誤を通じて学び、進んでいこうとする前向きな行動力を支える。
協調:共創し、協働しようとする価値観
全体像がつかめないような複雑な状況の中で、多様な視点を持ち寄り、共に意味をつくり出す力として機能する。
組織文化における3つの価値観の効果
BANI時代における不確実な環境は、私たちの判断や行動を困難にします。
そのような中で、クネビンフレームワークによって「状況に応じたアプローチ」が求められる一方で、それを支える組織文化=価値観の共有がなければ、柔軟な対応は根づきません。
ジェックでは、イノベーションに不可欠な「挑戦」「協調」「お役立ち」の3つの価値観と行動様式で表す組織文化を「集団性格」と呼んでいます。
この3つの価値観は、それぞれBANI時代に特有の困難さに対応する力を組織にもたらし、柔軟で意味ある判断と行動を実現する“土壌”となると考えています。
「お役立ち」の価値観による具体的な行動変化
組織内で「お役立ち」の価値観が根づいたとき、具体的な行動の変化が見られるようになります。
一部の例としてここでは3点挙げます。
- 「心理的安全性の向上」:失敗を学習の一部として捉えられるようになり、挑戦や発言が活性化する。
- 「共創の関係性」:部門や立場を超えて「一緒に創る」「助け合う」ことが自然に行われ、変化に対応しやすい組織になる。
- 「長期的な視点での意思決定」:目先の成果だけでなく、ステークホルダーや社会にとっての持続可能性を考慮した判断がしやすくなる。
つまり、「お役立ち道」は、BANIのような時代において、柔軟でしなやかな組織を支える基盤になると考えられます。
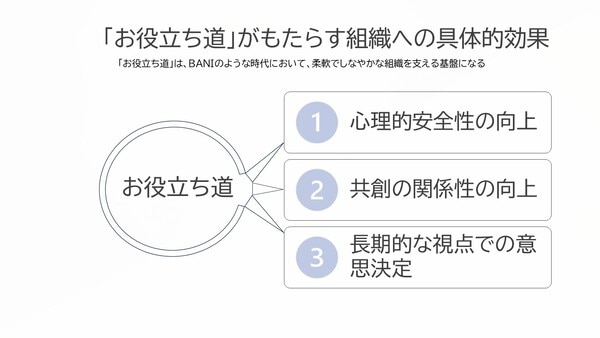
まとめ
不確実で先の見えないBANI時代において重要なのは、「未来を予測する力」ではなく、未来に向き合い続ける力です。
その力を育てるには、「状況を見極める知性(クネビンフレームワーク)」、「お役立ちの価値観の醸成」、「実行するリーダーシップ」が一体となって機能する必要があります。
しかし、「未来に向き合う力」は、一朝一夕で身につくものではありません。状況を見極め、価値観を共有し、行動を起こすことを積み重ねることで、その力は確実に養われます。BANI時代において、私たち一人ひとりが未来に向き合い続けることで、新たな可能性を切り拓いていきましょう。