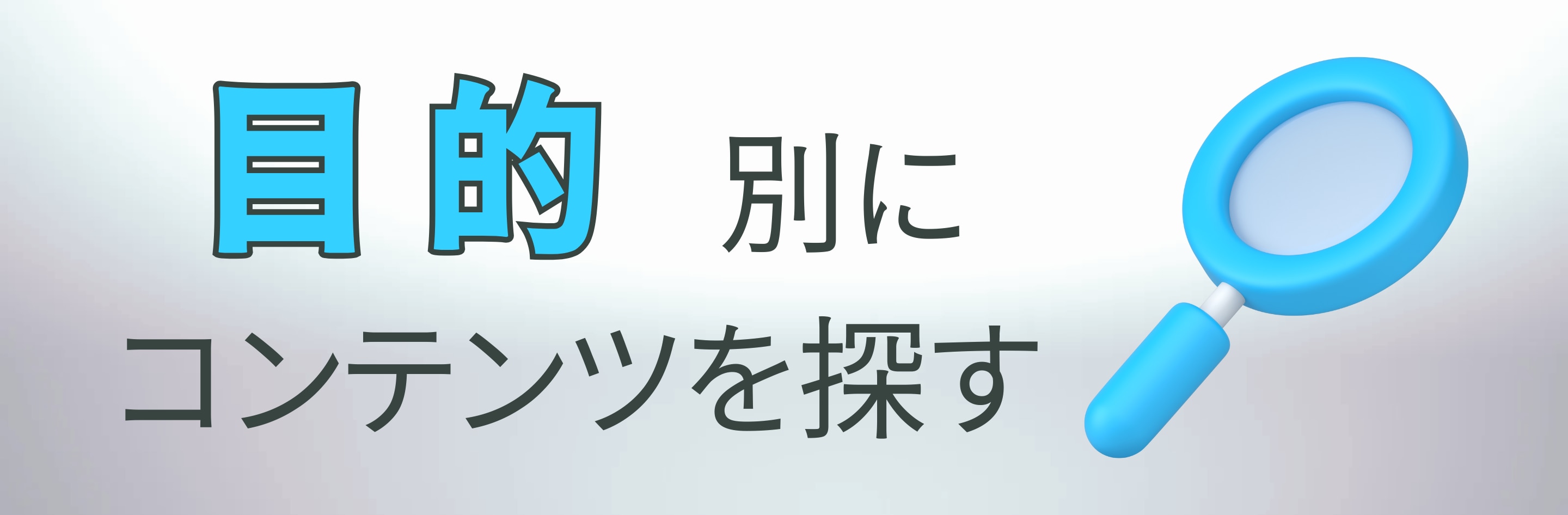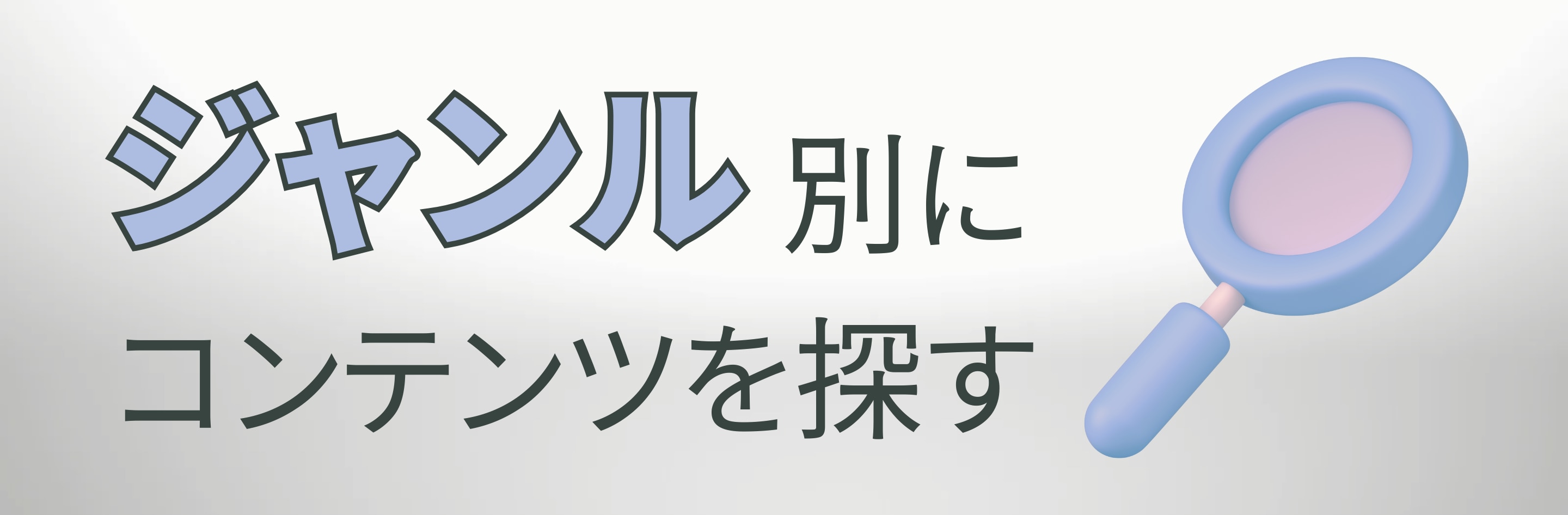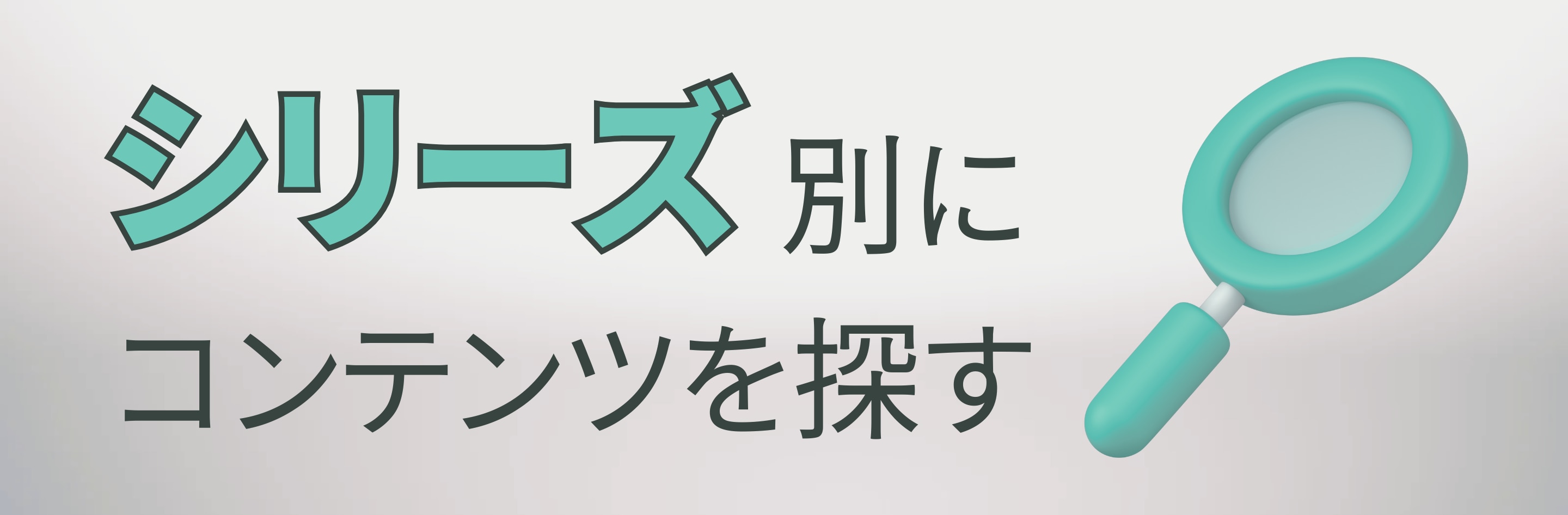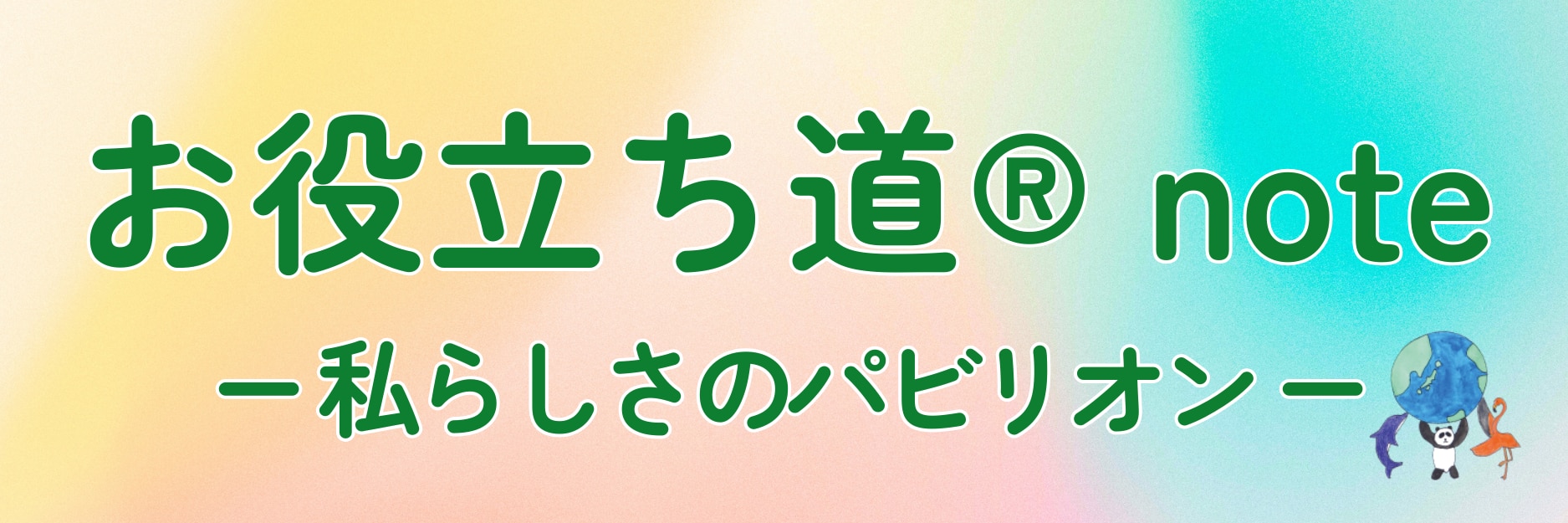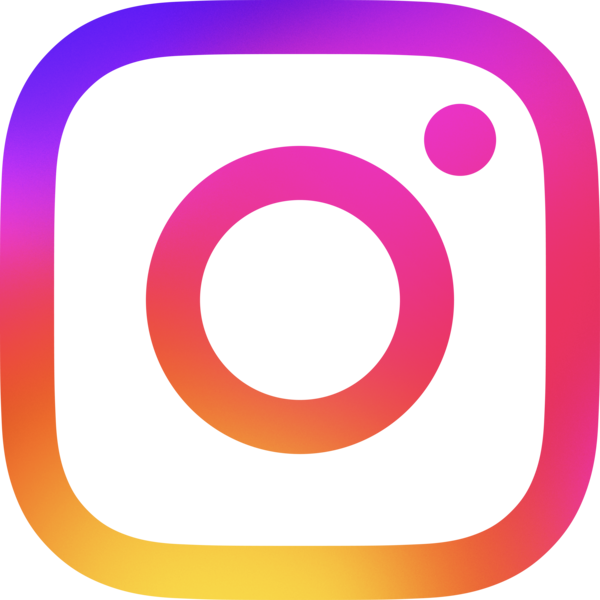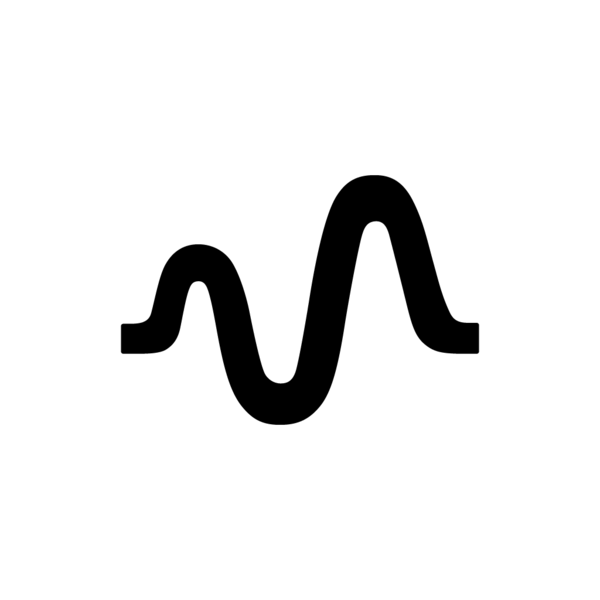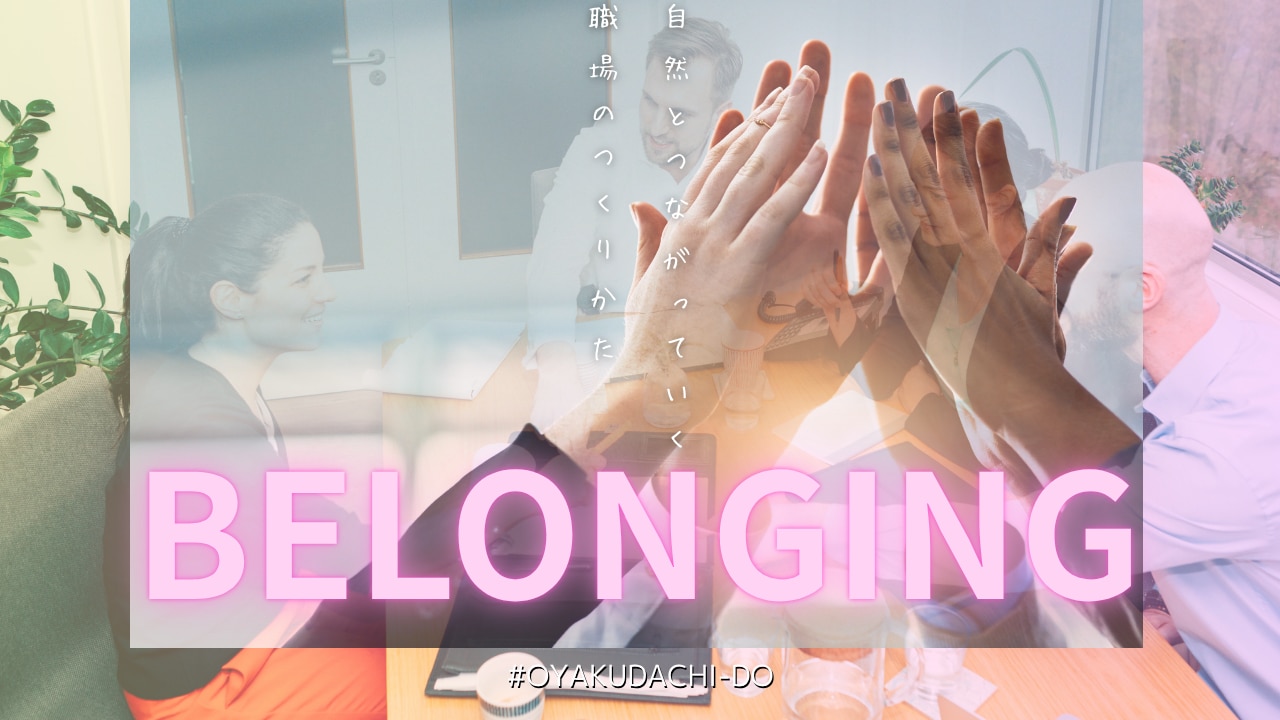
ビロンギング~誰もが自然とつながれる職場づくりの実践~
「なぜか居心地が悪い」「自分だけが浮いている気がする」──最近、職場でそんな声を耳にすることはありませんか? つながりの欠如を埋める「ビロンギング」
目次[非表示]
多様性が認められる時代だからこそ、「つながり」の欠如が問題になる
「なぜか居心地が悪い」「自分だけが浮いている気がする」──最近、職場でそんな声を耳にすることはありませんか?
現代の職場は、ダイバーシティ(Diversity)、エクイティ(Equity)、インクルージョン(Inclusion)、すなわち「DEI」への配慮が進みつつあります。多様な人材が受け入れられ、公平に機会が与えられ、意思決定や会話の場に参加できるという、いわゆる「形式的な受け入れ」は整ってきているのではないでしょうか。
しかし、DEIの取り組みが進んでいても、心理的な孤立感を抱く人が存在するという指摘もあり、「受け入れられている」という感覚とは別の次元の課題が浮かび上がってきています。
「ビロンギング」とは
このギャップを埋める鍵として、近年注目されているのが「ビロンギング(Belonging)」という概念です。これは、DEI(Diversity:多様性、Equity:公平性、Inclusion:包括性)の“その先”にある、心理的に「本当に受け入れられている」と感じる感覚を指します。
「ビロンギング(Belonging)」とは、所属を意味する単語「belong」が基になっており、所属、一体感、帰属意識のことを指します。自分を押し殺して会社に染まるのではなく、個性を生かしたまま心地よく組織に関与し、「居場所がある」と感じられる状態です(以降省略)。
出所:日本の人事部(https://jinjibu.jp/keyword/detl/1340/)
ある職場の食事会の事例
このビロンギングが欠けている状態は、形式的には受け入れられていても、心理的には孤立している状態を指します。以下に、日本の職場でありがちな例を紹介します。
―職場の食事会での事例―
・Diversity(多様性):部署全員が食事会に誘われている
・Equity(公平性):誰もが自由に食事や飲み物を選べる
・Inclusion(包括性):新人や立場の違う人にも話が振られる
ここまでは、DEI(Diversity:多様性、Equity:公平性、Inclusion:包括性) が機能しているように見えます。

しかし、
・会話は過去のプロジェクトや昔からの人間関係が中心で、新しく入ったメンバーは話についていけない
・話題に入ろうと気を遣って話しかけたり、リアクションを取ったりするが、どこか表面的なやりとりに感じてしまう
・一応その場にはいるものの、「本当に受け入れられているのだろうか?」という違和感や疎外感が残る
このように、「参加はできている」のに「心から楽しめない」「つながりを感じられない」といった状態こそが、ビロンギングが満たされていない状態なのです。
ビロンギングは「与えられる」だけでなく「育て合う」もの
ただし、ここで誤解してはならないのは、ビロンギングが「周囲から与えられるもの」だけではないという点です。
ビロンギングは、受け入れる側と受け入れられる側がともに「関係を育てる努力」をしてこそ、生まれるものではないでしょうか。
たとえば、新しく入ったメンバー自身も、周囲のメンバーの仕事ぶりや「お役立ちイメージ(「自分らしい役立ち方」をあらわしたもの)」に目を向け、「○○さんの段取りの仕方、すごく助かりました」といった感謝や共感の言葉を伝えることで、自ら「つながりの火種」を灯すことができます。
つまり、ビロンギングとは、「ここにいていいと思わせてほしい」と待つだけのものではなく、「ここにいたい」「一緒に働きたい」と思える関係を、自らの言葉と行動で育んでいこうとする意志こそが、真のビロンギングを生むと考えられます。
ビロンギングを支える「お役立ち道」の人間観
では、どうすればビロンギングを満たすことができるのでしょうか。
私たちジェックが提唱する「お役立ち道」には、そのヒントがあります。
お役立ち道では、人を「誰もが誰かの役に立ちたいという意識を持っている存在」として捉えています。これは、相手を信頼し、尊重する関係性の前提となる考え方です。
たとえば、新しく職場に入ったメンバーに対しては、単に「受け入れる」のではなく、「あなたの存在が必要であり、あなたの強みがここで活かされている」と実感できるような、温かく積極的な関わり方が求められます。
一方で、迎え入れられる側も、周囲の良さに目を向け、感謝や共感を言葉にして伝える姿勢が大切です。
こうした互いに価値を認め合い、支え合う関係が育まれることで、ビロンギングを支える豊かな土壌が形成されていきます。
「ここにいていい」と実感できる組織文化を
お役立ち道の文化とは、単に仕事で成果を出すだけでなく、「誰かの役に立ちたい」という内発的な意欲が共有され、活かされる文化です。
そこでは、一人ひとりが「お役立ちイメージ」を持ち、それがチーム全体で共鳴し合う関係が築かれています。
こうした文化の中では、形式的な多様性の尊重を超えて、「心からのつながり」が自然に育まれます。
それは、まさにビロンギングの実現であり、個人の成長と、組織の活力の源泉でもあるのです。
まずは、そばにいる誰かの「良さ」を伝えることから
ビロンギングは、制度だけではつくれません。
何よりも大切なのは、一人ひとりが「相手の存在を認め、関心を持ち、声をかけること」です。
今日、あなたが職場で交わす、たった一言が、誰かにとって「自分はここにいていい」と思える瞬間になるかもしれません。
──まずは、そばにいる人の「良さ」を伝えることから、はじめてみませんか?
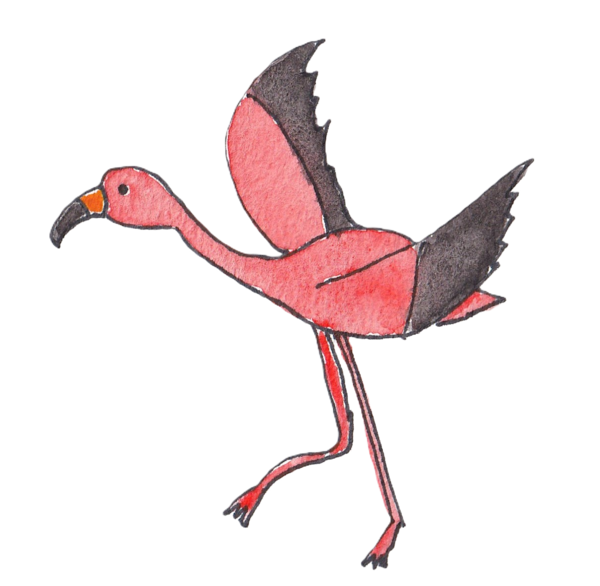
ネガティブ・ケイパビリティー悩んでも急がないのも勇気。ちょっと立ち止まるのもいいかもしれない。