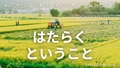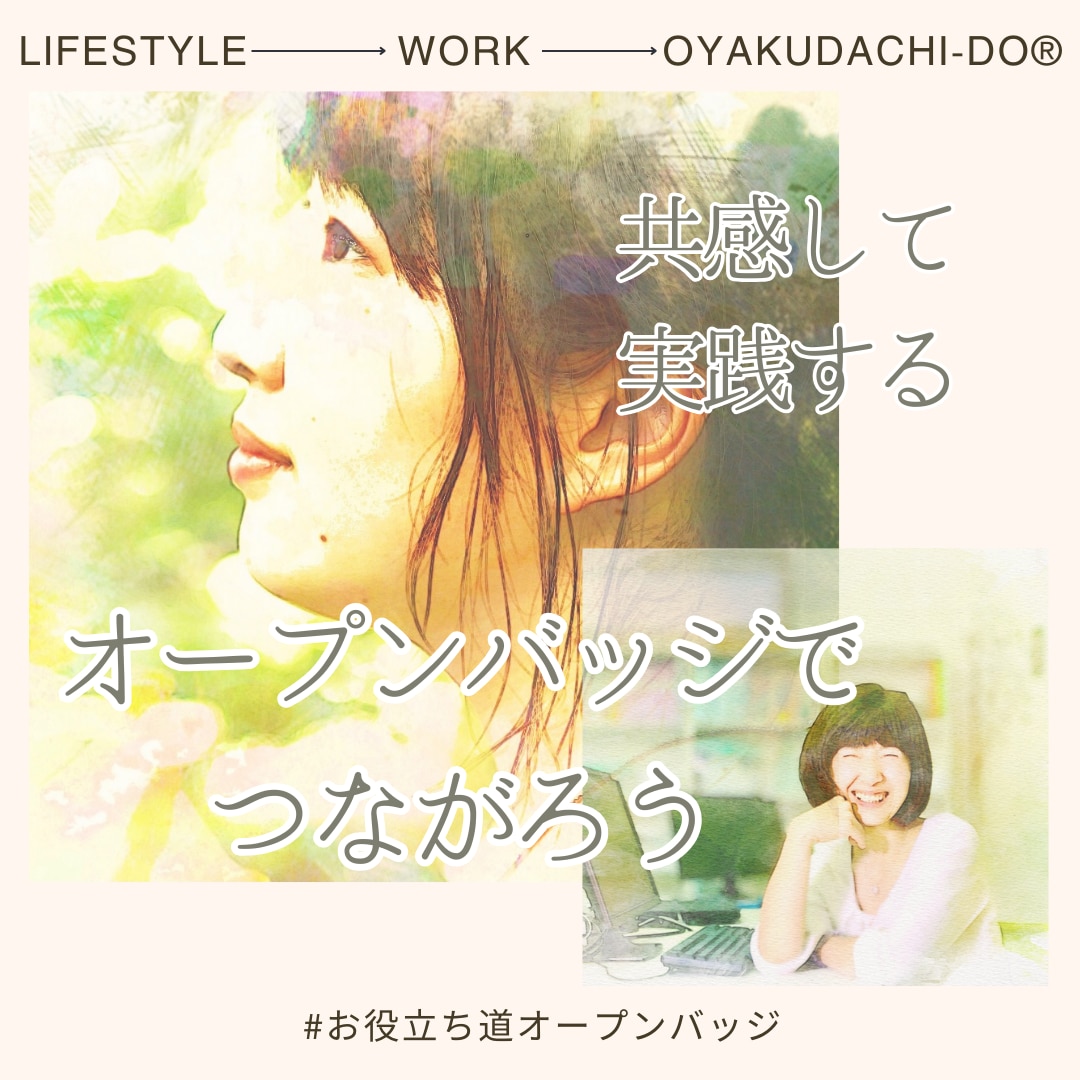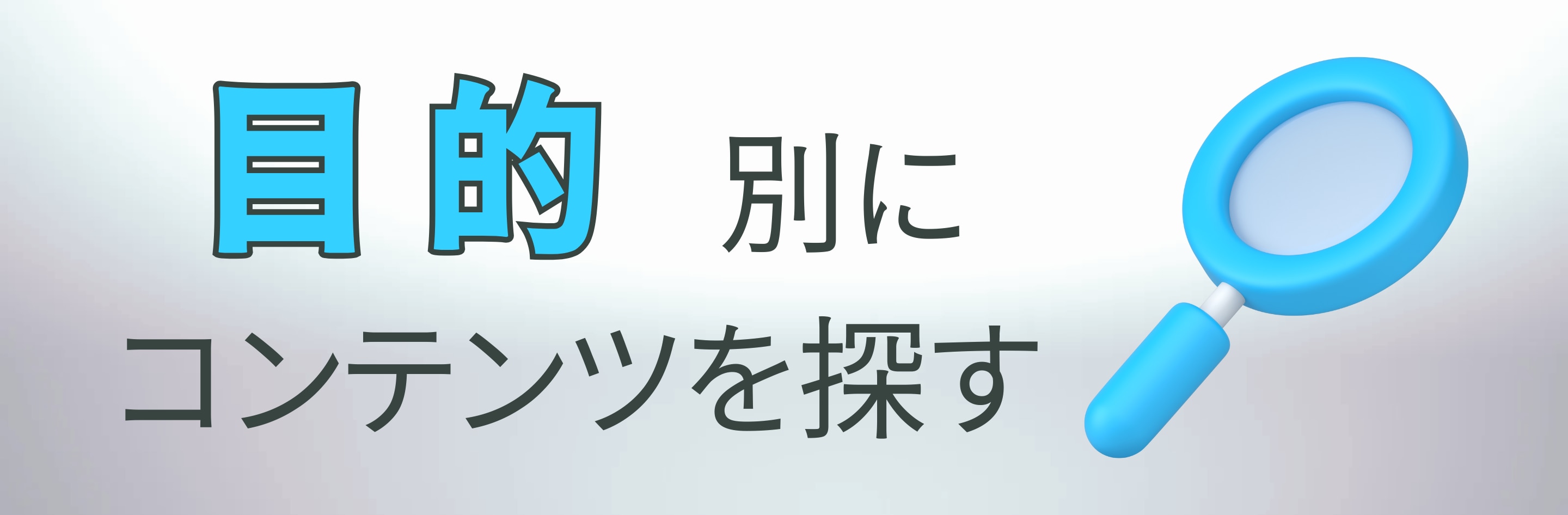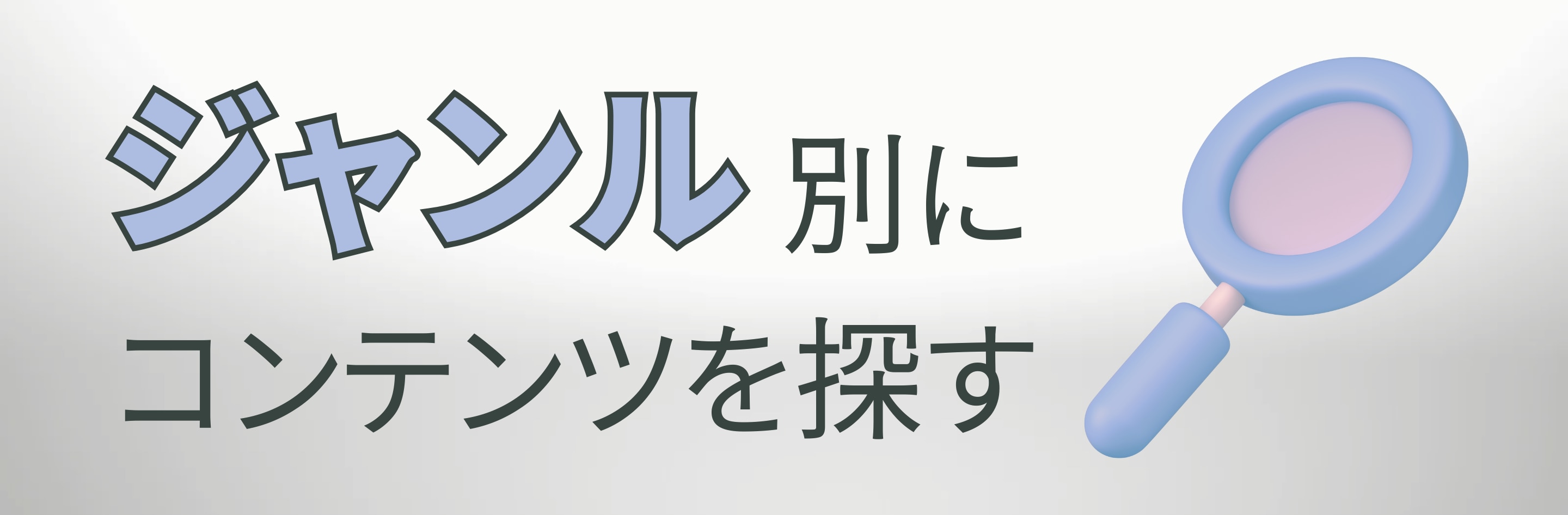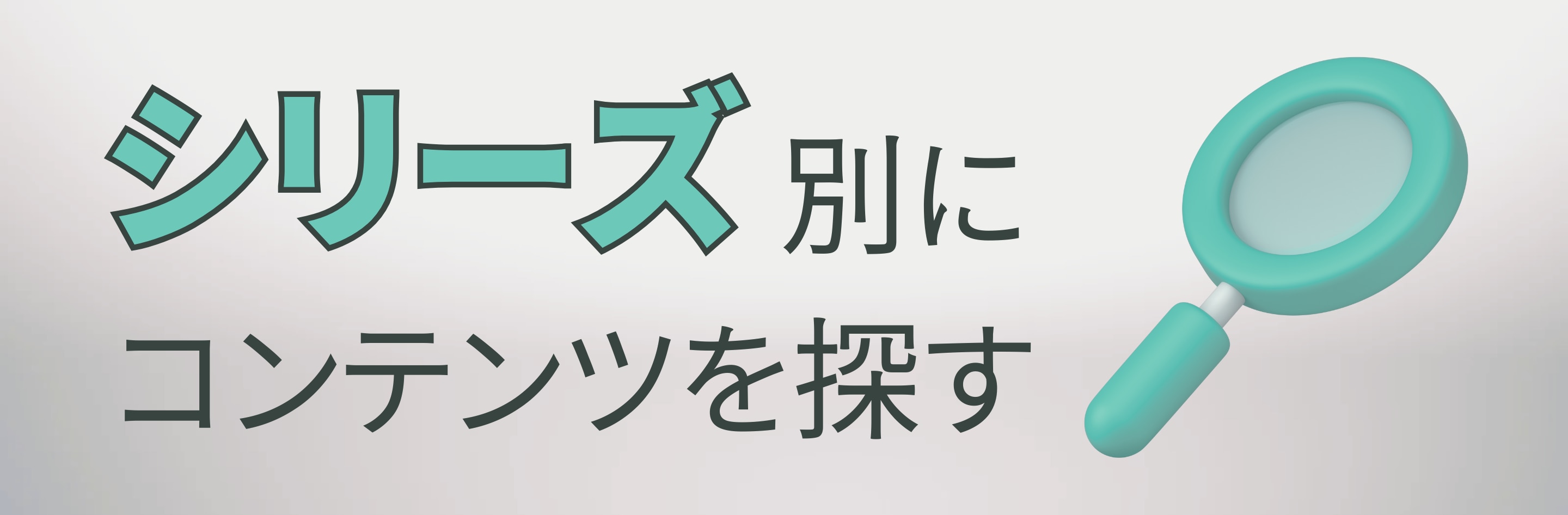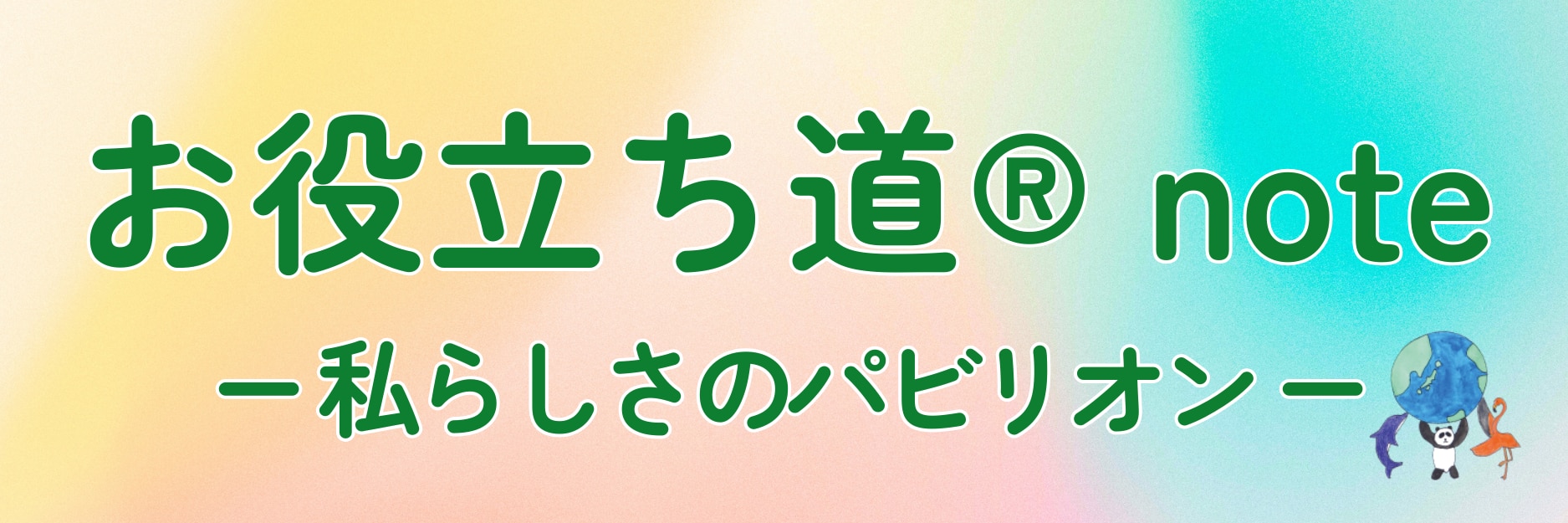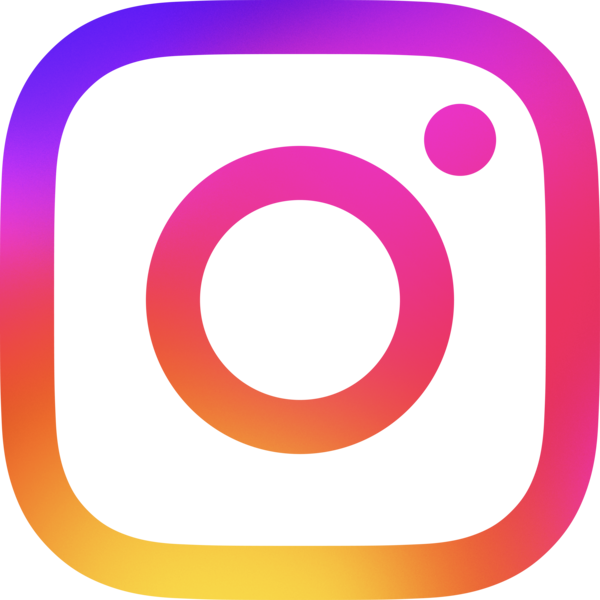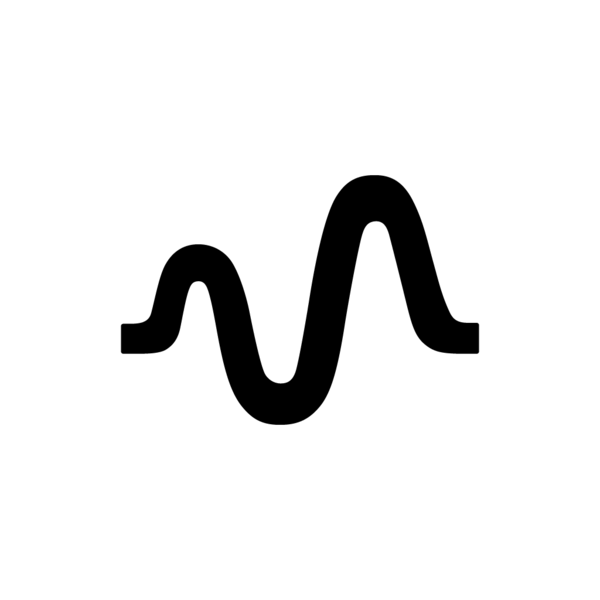ワクワクしながら働ける社会に感謝/勤労感謝の話
こんにちは。お役立ち道ねっとスタッフのたまです。
11月23日は「勤労感謝の日」。
この日は、「働く人」や「働けること」に感謝する日とされています。
でも今、私たちは「ただ働くだけ」で満たされているでしょうか?
むしろ、「どうせならワクワクしながら働きたい」「もっと意味のある仕事をしたい」——そのような想いを抱えている方も多いはずです。
では、「ワクワクしながら働く」とは、どういうことでしょうか?
古代の“労働”観
古代ローマ人にとって、「労働(labor)」は、肉体的にも精神的にも苦痛を伴う“罰”のようなものだったそうです。それはやがてキリスト教の広がりとともに、「労働は人間の罪に対する罰」とも解釈され、さらに“苦役”としての意味を強めていったそうです。
一方、日本における概念は、前述の労働観とは異なり、共同体の生存と繁栄、神々への奉仕、そして公的な義務として捉えられていました。人々は相互扶助の精神に基づき、肉体労働を含む営みを通じて社会秩序の中に位置づけられていたと言えます。つまり、 働くことは「苦しみ」ではなく、「社会を支える尊い営み」として価値づけられていたのです。
現代の私たちの「働く概念」やありたい姿
時代は変わり、私たちはいま、かつての「苦役としての労働」や「公的な義務」等ではなく、「価値を創る行為」としての働き方を模索しています。
とくに現代では、以下のような働き方が重要視されつつあります。
自己実現と社会貢献が両立する仕事
誰かの“ありがとう”とつながる活動
単なる義務ではなく、志を持って取り組む仕事
働くことは「何かを得る」ためだけでなく、「何かを与える」行為であるという視点が、今、求められています。つまり、「自己実現」という高次の欲求が下支えとなっています。
そうは言っても、現実は、生きていくためだったり、忙しさに追われたり、周囲との人間関係や組織の評価に苦しみ、働くこと自体に疲弊してしまう人も多いのではないでしょうか。
ありたい“勤労”の姿とは?
そのような中で、私たちは日々自分自身を振り返ります。
「働くこと」の価値とは何か?
そして、現代の私たちが目指す「ありたい勤労の姿」とは?
お役立ち道では、単なる作業や仕事を超えて、「誰か・何かの役に立つ」ことを軸に据えます。
たとえば、以下のような問いを通して、自分自身の働き方を見つめ直します。
自分が夢中になってきたこと(=お役立ちの源泉)は何か?
自分が実現したい社会の姿(=お役立ちビジョン)は何か?
今、自分は誰の、何の役に立っているのか?
こうした問いに向き合い、言語化し、行動に移していくプロセスそのものが、「お役立ち道」であり、「勤労=役立ちの誇り」として再構築していく営みなのです。
ワクワクしながら働きたい
なかでも、「ワクワクしながら働きたい」という感覚は、自分の中に眠る“お役立ちの源泉”が動き出すサインです。
誰かに喜ばれたとき
自分のアイデアが社会に届いたとき
チームで協力して成果を出せたとき
そのような瞬間に、人は「働くこと」に手応えと喜びを感じます。一人でもワクワクできますが、誰かと一緒に同じ志を持ってワクワクしたほうが、ワクワクが何倍にもなります。
だからこそ、その瞬間や感覚を逃さないようにしたいものです。
そして、「ワクワクしたい」という生きるうえでの根源的な欲求と「働く意味」がつながった時、人や組織のパフォーマンスが最大限に発揮される時ではないでしょうか。
それが社会的に、認められ、奨励されている社会に感謝したいと思います。
👯ワクワクする根源は何か?見つけませんか?