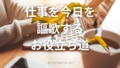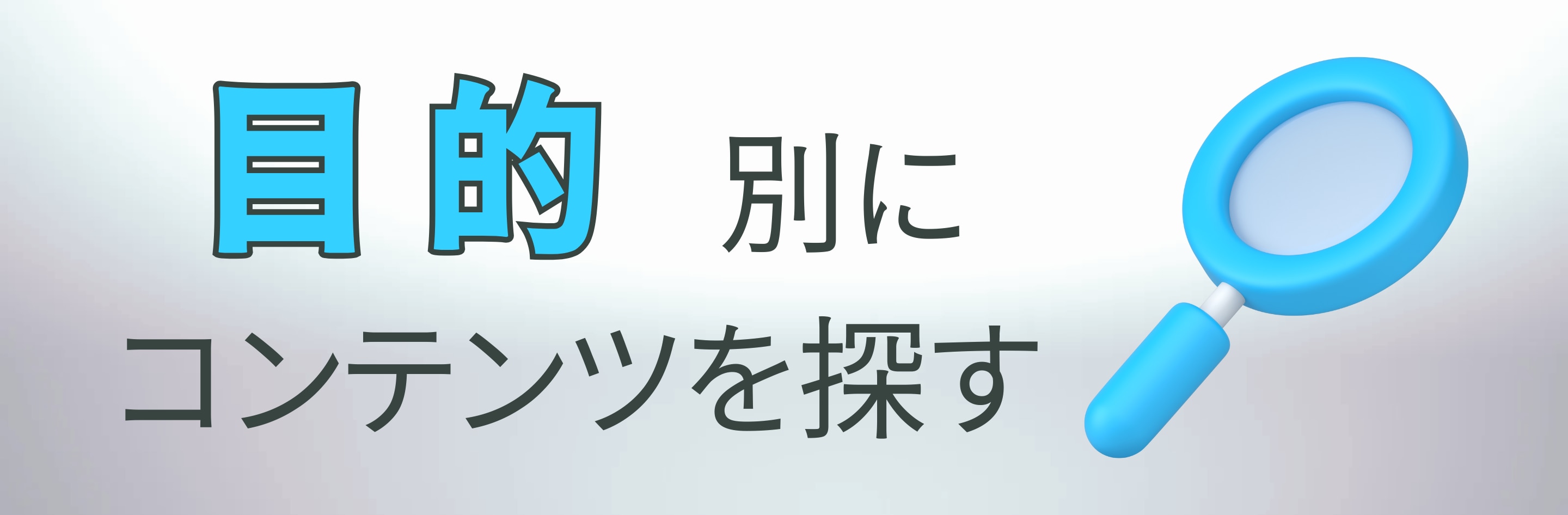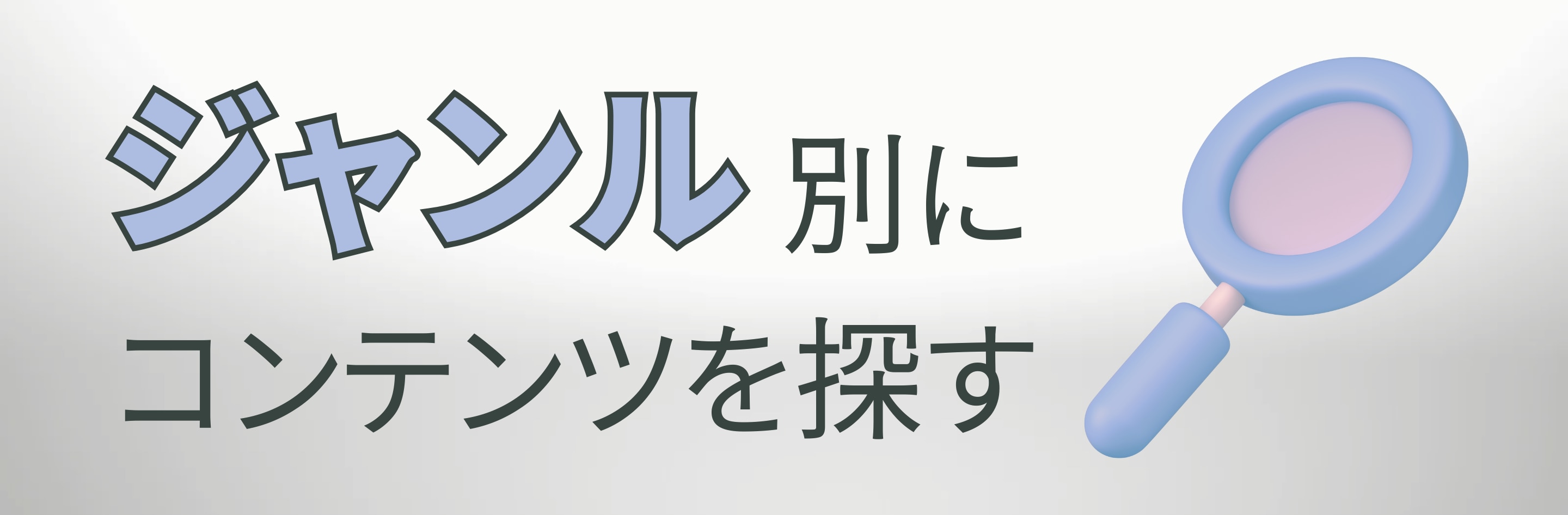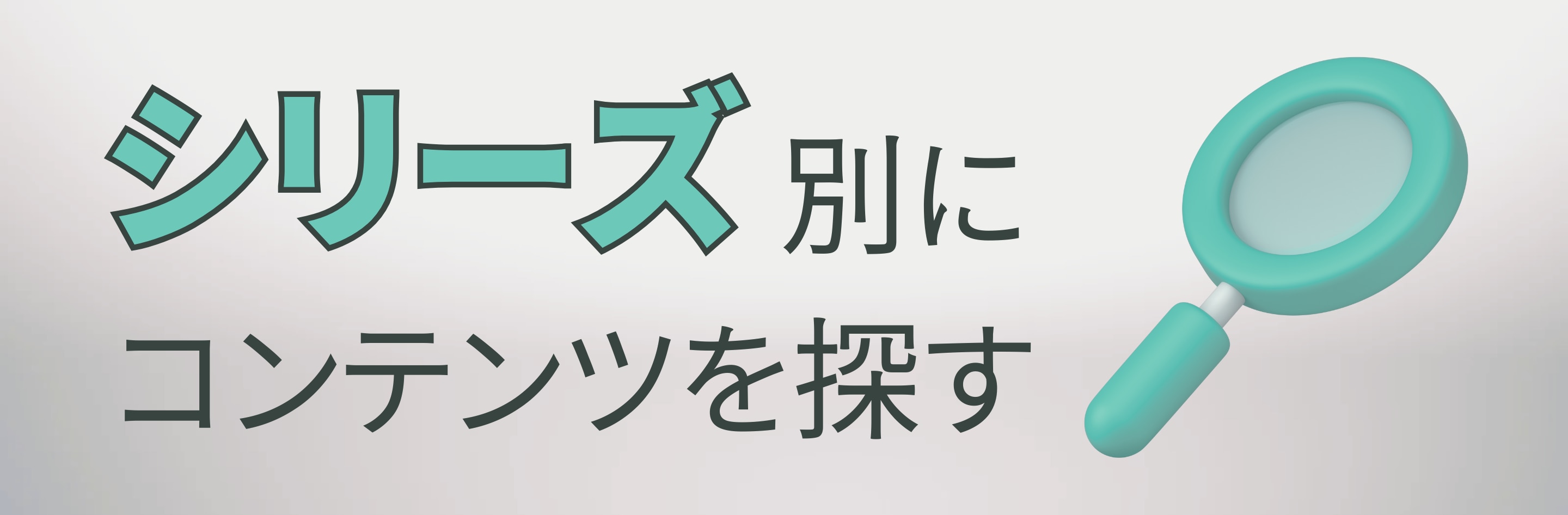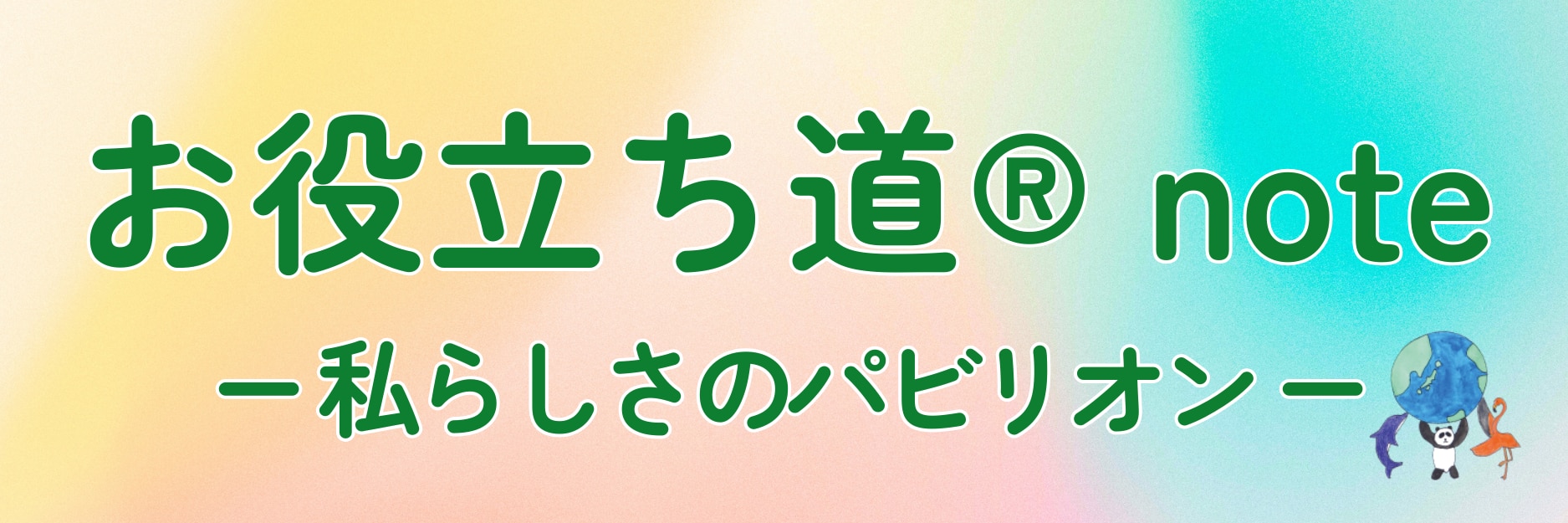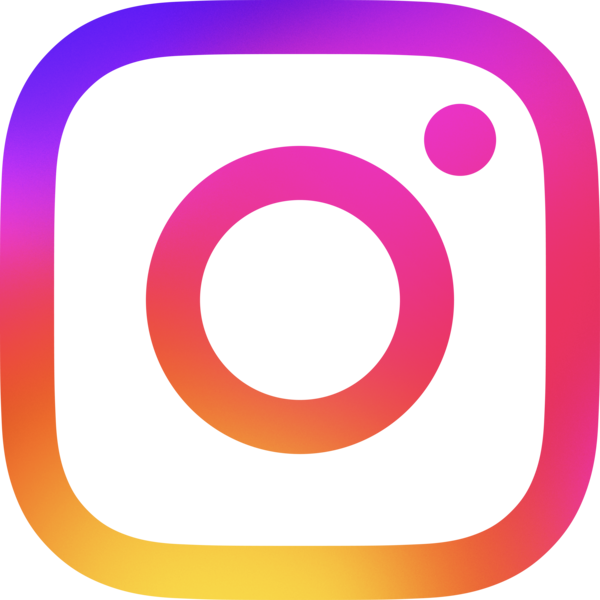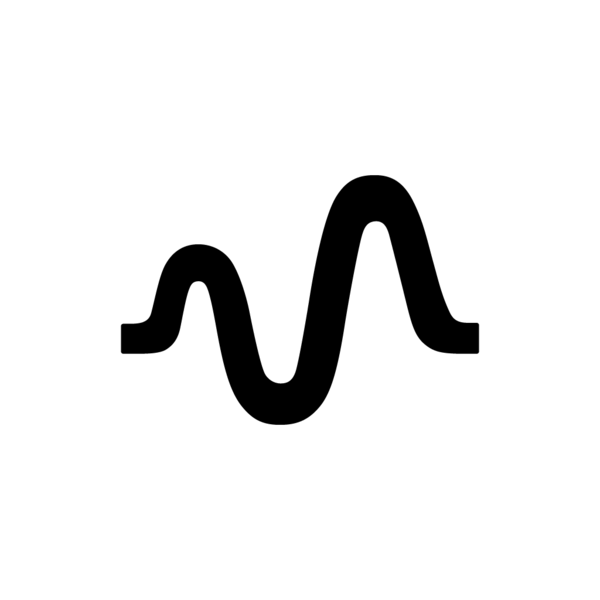マーケティングの新定義とお役立ち創造 ─「売る」から「価値共創」へ
マーケティングは「売る」ことから「価値を共創すること」へと進化しています。それを「お役立ち道」の観点から読み解き、企業や個人のあり方にどのような変革を促すのかを考えてみましょう。
マーケティング定義の刷新
2024年、マーケティング定義が34年ぶりに刷新されました。公益社団法人日本マーケティング協会が、2024年に新しい「マーケティングの定義」を発表しました。これは1990年の定義以来、約34年ぶりの大幅な見直しです。
この改訂は、社会や顧客といったステークホルダーとの共創や、持続可能性への視点を重視するなど、時代の変化を的確に反映したものとなっています。
マーケティングの定義(2024年制定)
(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。
注 1)主体は企業のみならず、個人や非営利組織等がなり得る。
注 2)関係性の醸成には、新たな価値創造のプロセスも含まれている。
注 3) 構想にはイニシアティブがイメージされており、戦略・仕組み・活動を含んでいる。
1990年に制定されたマーケティングの定義
マーケティングとは、企業および他の組織1)がグローバルな視野2)に立ち、顧客3)との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動4)である。
1)教育・医療・行政などの機関、団体などを含む。
2)国内外の社会、文化、自然環境の重視。
3)一般消費者、取引先、関係する機関・個人、および地域住民を含む。
4)組織の内外に向けて統合・調整されたリサーチ・製品・価格・プロモーション・流通、および顧客・環境関係などに係わる諸活動をいう。
出典:日本マーケティング協会 2024年1月25日発表
https://www.jma-jp.org/info/news/916-marketing
この定義から、違いは以下のように考えられます。
新旧マーケティング定義の比較から見える変化
観点 |
1990年定義 |
2024年定義 |
マーケティング観 |
「マーケティングとは ・・・活動である」 |
「マーケティングとは ・・・構想でありプロセスである」 |
目的・焦点 |
市場創造のための総合的活動 (やや供給者側視点) |
価値共創とステークホルダー関係の 醸成、持続可能な社会 (より双方向・公共性重視) |
対象の中心 |
顧客との相互理解 |
顧客および社会との価値共創 |
このように、1990年の定義では「企業が顧客と向き合い市場を創る」という片方向性が強いのに対し、2024年の新定義では「企業と社会が共に価値を創る」双方向・循環的な構想に変化しているといえます。
「構想」としてのマーケティング:実装を伴う設計思想へ
2024年のマーケティング定義における「構想」という言葉は、単なる理念やビジョンにとどまらず、未来への構想力と、それを実現する戦略・仕組み・活動を包括する「実装を伴う設計思想」を意味しています。この定義は、ジェックが長年にわたり提唱してきた「お役立ち道」の思想や「お役立ち創造」の実践に深く共鳴するものです。
この記事では、「売る」ことに主眼を置いていた従来のマーケティング観から、「価値を共に創る構想」へと進化した現代のマーケティングの本質を、「お役立ち道」の観点から読み解き、企業や個人のあり方にどのような変革を促すのかを考えてみます。
「売る技術」から「価値を共に創る構想」へ
かつてのマーケティングは、製品やサービスを「いかに売るか」という販売促進の技術に重点が置かれていました。たとえば、顧客に「何が欲しいか」を尋ねてその要望に応える発想や、経験・勘・度胸(K.K.D.)や義理・人情・プレゼント(G.N.P.)といった人間関係に依存する営業スタイルが一般的でした。
しかし、現代の成熟社会においては、こうした「売る技術」だけでは企業の持続的な成長は望めません。企業は単なる営利主体ではなく、「社会にとっての存在意義が問われる公共的存在」へと変わりつつあります。
「お役立ち創造」が求められる時代
このような時代において求められるのが、お客様が「その先のお客様の課題」そして「社会課題」にもっともっとお役に立てる価値を創造するという『お役立ち創造』の視点です。お役立ち創造とは、単なるニーズ対応や需要創造を超えて、お客様と共に「未来の意味」や「社会課題との接続」を構想し、お客様自身の成果と持続可能性を高めていくプロセスです。
企業は、お客様に製品やサービスを売るだけでなく、「あなたのお役立ちが、さらに社会のお役立ちへとつながる」ように支援することが求められます。このようなアプローチによって、お客様は市場で選ばれ続け、自社の価値もまた自然と高まっていくのです。
つまり、マーケティングとは今や「売る」ことではなく、「お役立ちの構想力を通じて、社会との価値の連鎖を生み出す営み」へと変貌しています。その実現には、理念の提示にとどまらず、戦略・仕組み・活動へとつながる具体的かつ継続的な働きかけ=イニシアティブが不可欠です。
こうしたマーケティングの捉え方の変化は、企業においては「何を売るか」ではなく、「誰のために、どのような未来を構想するか」が問われる時代の到来を意味します。そして個人においても、「成果」や「評価」といった従来の指標よりも、「いかに価値あるつながりを共創できるか」が、新たな行動原理となりつつあるのです。
このように、現代のマーケティングは「商品を届ける技術」から、「社会と共に価値ある未来を描き、実装していく力」へと進化しています。
そしてこの進化は、私たちが追求してきた『お役立ち創造』という営みと、深いレベルで共鳴しているといえます。
終わりに:「売る力」から「構想し共創する力」へ
未来は「売る力」ではなく、「構想し共創する力」によってひらかれます。
私たち一人ひとりが、「誰のために、どのような価値を生み出したいのか」を問い直すことが、企業にも社会にも、お役立ちの連鎖を起こしていく第一歩となります。
ぜひ、皆さん自身の現場でも、「お役立ち創造」に向けた新しいマーケティングの在り方を探ってみてはいかがでしょうか。
価値を共創できる企業への変革~価値共創型組織ソリューションでお役立ちの実現~